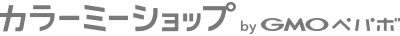ЅАЅщЅєЅЭЅыЁЁЅэЅУЅНЁІЅыЅЄЁМЅЮ2005ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЁЁЅэЅУЅНЁІЅыЅЄЁМЅЮ2005ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬ
ЅэЅУЅНЁІЅыЅЄЁМЅЮ2005ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬЄЧЄЙЁЊ
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭАЗЄЄЄЮЅеЅъЅІЁМЅъЄЮНХФУ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЧЄЙЁЃ
ЄГЄЮЄиЄѓЄЮЅьЅйЅыЄЮЅяЅЄЅѓЄШЄЪЄыЄШ
ХіХЙЄЮЄДОвВ№БОЁЙЄЧЄЩЄІЄШЄЪЄыТЄЄъМъЄЕЄѓЄЧЄЯЄЪЄЏ
ЛдОьЄЮЄІЄЭЄъЄЮУцЄЫ
ХіХЙЄтЄСЄчЄУЄШЄРЄБКЎЄЖЄщЄЛЄЦЄЄЄПЄРЄЄЄЦЄЄЄы
АЗЄяЄЕЄЛЄЦЄтЄщЄУЄЦЄЄЄы
ЄНЄѓЄЪЅьЅйЅыЄШЄЪЄъЄоЄЙЄЌ
ЛфЄтОмЄЗЄЏЄЯУЮЄъЄоЄЛЄѓЄЌ
КЃЄоЄЧЄтфўЭОЖЪРоЄЂЄУЄЦЄЮКЃЄЌЄЂЄыТЄЄъМъЄЕЄѓЄЮЄшЄІЄЧ
ЄШЄЪЄыЄШ
КЃИхЄт
ВСГЪЬЬЄтДоЄсЄЩЄІЄЪЄУЄЦЄЄЄЏЄЮЄЋ
ЄЩЄІЄЄЄУЄПЪ§ИўРЄиЄШПЪЄѓЄЧЄЄЄЏЄЮЄЋ
СДЄЏЄяЄЋЄщЄЪЄЄ
ЄРЄЋЄщЄГЄНКЃЄЂЄыЕЎНХЄЪЅяЅЄЅѓЄђТчЛіЄЫЄЗЄЦЄЄЄЏЄГЄШЄтЩЌЭзЄШ
ЛзЄЈЄыЅяЅЄЅѓЄРЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
ХіХЙЄЮЄЊМшАњЄЮУцЄЧЄт
МЋСГЧЩЅяЅЄЅѓБОЁЙДиЗИЄЪЄЏ
АІЄЕЄьЄы
ДЖЦАЭПЄЈЄыЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓ
ЄГЄГПєЧЏЄЮЄІЄСЄЫАьЕЄЄЫВСГЪЄЮЙтЦЄШЄЪЄУЄЦЄЄЄыЅяЅЄЅѓ
ЄЧЄтЄГЄЮЅяЅЄЅѓЄЫДиЄЗЄЦЄЯРЕФОСДЄЏЧМЦРЄЄЄЏШЯАЯЄЪЄЮЄЋЄЪЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
КЃВѓПЗЄПЄЫХіХЙЄЫХўУхЄЗЄПЅяЅЄЅѓ
ЁћЅъЅмЅУЅщ2014ЧЏ
КЃВѓ2014ЧЏЄЯАћЄѓЄЧЄЊЄъЄоЄЛЄѓЄЌ
АЪСА08АћЄѓЄРЄШЄЄЮДЖЄИЄЧЄЙЁЃ
ЅъЅмЅУЅщЅИЅуЅУЅщЄЮ2008ЧЏАћЄпЄоЄЗЄП
РЕФОНщЦќЄЮУЪГЌЄЧ
ЄНЄЮИЗЄЗЄЕЄШЄЄЄІЄЋЅЙЅШЅЄЅУЅЏЄЕЅЏЁМЅыЄШЄЄЄІЄшЄъЄЯ
РкЄъЮЉЄУЄПЛГЄШЄЋИЗЄЗЄЕЄЌЄЂЄыЅяЅЄЅѓЄШДЖЄИЄЦ
08ЄЪЄЋЄЪЄЋТчЪбЄЋЄЪЄШЛзЄЄЄЄф
ЄГЄьЄЌЦѓЦќЬмЛАЦќЬмЄШЄЩЄѓЄЩЄѓФДЯТЄЗЄЦЮЩЄЄЪ§ИўЄиЄШИўЄЋЄУЄЦЄЄЄЏЅяЅЄЅѓ
ПЇЄЯЅЊЅьЅѓЅИУуЗЯЄЧЄтЅЏЅъЅЂЁМЄЧ
ЄГЄЮПЇФДЄтЦѓЦќЬмЛАЦќЬмЄШЄшЄъУуПЇЄГЄВУуЗЯС§ЄЗЄЦЄЄЄЏ
С§ЄЗЄЦЄЄЄЏЄШЄшЄъПЇЄЌНаЄЦЄЏЄыЄЪЄѓЄЋЮЩЄЕЄЌНаЄЦЄЏЄыЩдЛзЕФЄЪЅяЅЄЅѓ
ЅЊЅьЅѓЅИВЬШщДЖЄЂЄъ
ДЛЕЬЅЗЅэЅУЅзФвЄБЅЗЅъЅЂЅыЄЕЄЂЄъЅЩЅщЅЄЄЪЄЮЄЫЬЊДЖЄтЄЂЄы
ЖьЬЃЄтОЏЁЙЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄЮНТЁЉГСНТЄЮЄшЄІЄЪЅПЅѓЅЫЅѓ
ЄЪЄЋЄЪЄЋЄЫЙХЧЩЄЪДЖЄИЄЧЄЗЄПЄЌ
АћЄрЄДЄШЄЫОЏЄЗЄКЄФЬЅЮЯЄђВђЪќЄЕЄЛЄЦЄЄЄЏЄшЄІЄЪ
ЦѓЦќЬмАЪЙпВЬМТЄЮЅЫЅхЅЂЅѓЅЙЄтНРЄщЄЋЄЏЅЩЅщЅЄЄЕЄЯЄЂЄъЄЪЄЌЄщЄт
ЬЉХйДЖЄфПМЄпЄЯС§ЄЗЄЦЄЄЄЏЅПЅѓЅЫЅѓЄЮНТЄпЄЪЄЩЄтЭЯЄБЙўЄѓЄЧФДЯТЄЗЄЦЄЄЄЏЭЭЄЌДЖЄИЄщЄьЄоЄЙЁЃ
ЅрЅѓЅрЅѓЄШЄЗЄПЬРЄыЄЄЖЏЄЕЄфТРЄЕЄЯЬЕЄЏЄШЄт
ЦтЪёЄЙЄыЅЈЅЭЅыЅЎЁМЄЪЄЩЄЯСЧРВЄщЄЗЄЏ
ЅЗЅъЅЂЅЙЄЪПМЄп
ЅпЅЭЅщЅыДЖЄЪЄЩЄЯЄшЄъ08ЄЮЄлЄІЄЌДЖЄИЄщЄьЄоЄЙЄЗ
ИМПЭМѕЄБЄЙЄыЄоЄРРшЄНЄЗЄЦЄЕЄщЄЫБќЄЌЄЂЄъЄНЄІЄЪЕЄЄЫЄЪЄыЅяЅЄЅѓ
ЄНЄѓЄЪЕЄЄЌЄЄЄПЄЗЄоЄЙЁЃ
ЅЂЅыЅГЁМЅыХйПєЄЯ14,5%ЁЊ
АЪВМЅЄЅѓЅнЁМЅПЁМЭЭО№Ъѓ
ЅшЅЙЅГЄЌХкУЯЄђКЧЄтЩНИНЄЙЄыЩЪМяЄШЙЭЄЈЄыЅъЅмЅУЅщ ЅИЅуЅУЅщЁЃ2012ЧЏЄђКЧИхЄЫЅъЅмЅУЅщ ЅИЅуЅУЅщАЪГАЄЮЧђЅжЅЩЅІЄЮМљЄЯАњЄШДЄЋЄьЁЂ2013ЧЏАЪЙпЄЮЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЧђЅяЅЄЅѓЄЯЅъЅмЅУЅщЄЮЄпЄШЄЪЄУЄПЁЃ
ЅЂЅѓЅеЅЉЅщЁЪСЧОЦЄЄЮсБЁЫЄЧЬѓШОЧЏДжШщЄДЄШЄЮШАЙкЄШНЯРЎЄђЙдЄЄЁЂАЕКёИхКЦЄгЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄиЄШЬсЄЗШОЧЏДжНЯРЎЁЂЄНЄЮИхТчУЎЄЧЬѓ6ЧЏДжНЯРЎЄЕЄЛЄшЄІЄфЄЏЅмЅШЅъЅѓЅАЄЕЄьЄыЁЃ
МЁЄЯ
ЁћЅэЅУЅНЁІЅжЅьЅА2004ЧЏ
ЅэЅУЅНЁІЅжЅьЅА04ЄШЅэЅУЅНЁІЅыЅЄЁМЅЮ03ЄЯ
ЄРЄЄЄжСАЄЫОЏЮЬЄРЄБЄЄЄПЄРЄЄЄЦЄЊЄъ
ЄНЄьЄђПВЄЋЄЛЄЦЄЄЄПЅяЅЄЅѓЄШЄЪЄъЄоЄЙЁЃ
ЅЄЅйЅѓЅШЄЧАћЄѓЄРЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓ
ЧђЄтРЈЄЄЄЮЄЧЄЙЄЌ
РжЄтЄГЄьЄЯЄоЄПЄЪЄѓЄШЄЄЄІЄЋЄЩЄЪЄПЄЫЄтДЖЄИЄЦЄЄЄПЄРЄБЄы
СдТчЄЕЄЂЄыЅяЅЄЅѓЄЧЄНЄЮДЖЄИЄЋЄщ
ПєЧЏПВЄЋЄЗЄЦЄЊЄЄПЄЄЄЪЄШЛзЄУЄПЅяЅЄЅѓ
ЄНЄЮЅэЅУЅНЁІЅжЅьЅА2004ЧЏ
КЃВѓ2024ЧЏ9ЗюЄЫЄЄЄПЄРЄЄоЄЗЄПЁЃ
СлСќЄЯЄЗЄЦЄЊЄъЄоЄЗЄПЄЌ
ЄфЄЯЄъРЈЄЄЅяЅЄЅѓ
ШДРђЄЗЄПНжДжЄЫЄЋЄЪЄъЙШЯАЯЄЫЙсЄъЄЮЙЄЌЄъЄНЄЗЄЦОхМСЄЪЩђЦКЄЮЙѕЬЃЄЌ
ЙЄЌЄыДЖГаЄЂЄъ
АЮТчЄЪЅяЅЄЅѓЄЫЄЂЄыЄНЄьЄЧЄЙЄЭ
ЙсЄъЄЮЬЉХйЄЌРЈЄЄЄЮЄЧЄЙЄЌ
РжЙѕЄЄЄГЄьЄоЄПхЬЬЉЄЪБеТЮ
ЩђЦКДЖЄШУЎДЖЄГЄьЄЌЄоЄПРфЬЏЄЪЅаЅщЅѓЅЙЄЧТИКпЄЙЄыЅяЅЄЅѓЄЧ
УЎДЖЄтЬЕТЬЄЫЄЯНаЄЕЄЪЄЄЄЌЛйЄЈЄШЄГЄЮНХИќЄЪУцЄЫЩЪЄђЭПЄЈЄы
ЄцЄУЄПЄъЄШЄНЄьЄЧЄЄЄЦЦВЁЙЄШЄЗЄЦФУКТЄЙЄыЅяЅЄЅѓ
ЄНЄГЄЋЄщХкЄЮЄЕЄщЄЫЅЅЮЅГЗЯЄтЅШЅъЅхЅеЄЮЄшЄІЄЪДЖГаГаЄЈЄыЄЮЄЯ
ЄЪЄѓЄЧЄЗЄчЄІЄЋ
ЅЅЮЅГНаНСЗЯЄЮЅЪЅСЅхЁМЅыЄЯЄЂЄъЄоЄЙЄЌ
ЄНЄьЄщЄШЄЯЪЬЪЊЄЮЄтЄЮ
ЅжЅыЁМЅйЅъЁМЄЮЖХНЬЄЗЄПЄшЄІЄЪВЬМТЬЃЄтИќЄпЄШЬЉХйЄШЄоЄэЄфЄЋЄЪЩїЬЃ
ЩхЭеХкЄЮЅЫЅхЅЂЅѓЅЙЄЪЄЩЄтЭэЄпЙчЄЄ
ЅэЁМЅЙЅШЙсДХЄфЄЋЄЪЦАЄЄЋЄщЅщЅрЅьЁМЅКЅѓЄиЄШ
ЄцЄУЄПЄъЄШЅгЅэЁМЅЩЄЮЄДЄШЄЏСЧРВЄщЄЗЄЅЦЅЏЅЙЅСЅхЅЂЄЂЄыБеТЮ
АћЄпПЪЄсЄЦЄтАћЄпПЪЄсЄЦЄт
ЄГЄьЄРЄБЄЮЧЎЮЬЄШЅмЅъЅхЁМЅрДЖЄЂЄъЄЪЄЌЄщ
ЄЏЄЩЄЄЄШДЖЄИЄыЄГЄШЄЌЬЕЄЄ
ЩдЛзЕФЄЧЄЂЄъЄГЄьЄЌЄоЄПАЮТчЄЪЅяЅЄЅѓЄЮЦУФЇЄЧЄтЄЂЄыЄЮЄЋ
ВСГЪЙтЦИЗЄЗЄЄЙтЕщЅяЅЄЅѓ
КЃЄЧЄЯ5Ыќ10ЫќХіЄПЄъСАЄЮРЄГІЄЧЄЙЄЮЄЧ
ЄНЄьЄЪЄѓЄЋЄшЄъЄтВПЄЋСЧРВЄщЄЗЄРЄГІИЋЄЛЄЦЄЏЄьЄыЄНЄѓЄЪЅяЅЄЅѓЄЧЄЯЄШ
ЛзЄУЄЦЄЗЄоЄІЅяЅЄЅѓЄЧЄЙЁЃ
ЄтЄІАьЄФПВЄЋЄЛЄЦЄЄЄПЅяЅЄЅѓ
ЁћЅэЅУЅНЁІЅыЅЄЁМЅЮ2003ЧЏ
ЅэЅУЅНЁІЅжЅьЅАЄшЄъЄтЄЕЄщЄЫЅъЅМЅыЅєЅЁХЊТИКпЄШЄЪЄы
ЄГЄЮЅяЅЄЅѓ
ЅгЅѓЅЦЁМЅИЄЌ2003ЧЏЄШЄЄЄІЄГЄШЄЧ
ЛфЄЫЄШЄУЄЦЄтЦУЪЬЄЪЅгЅѓЅЦЁМЅИ
КюЪСХЊЄЫЄЯ
03ЄшЄъЄт04ЄЮЄлЄІЄЌШцГгХЊЮЩЄЄЄШЄЕЄьЄыЅгЅѓЅЦЁМЅИЅСЅуЁМЅШЄтЄЂЄыЄшЄІЄЧЄЙЄЌ
ЛфЄЫЄШЄУЄЦЄЯЄНЄѓЄЪЄЮДиЗИЄЪЄЄ
ЄфЄЯЄъЦУЪЬЄЪ03ЄЧЄЙЁЃ
ЄГЄСЄщЄЯЄЕЄЙЄЌЄЫЅЦЅЄЅЙЅЦЅЃЅѓЅАЄЯЄЧЄЄоЄЛЄѓЄЮЄЧ
ЅЄЅѓЅнЁМЅПЁМЭЭО№ЪѓЄЮЄпЄЧЄЙЁЃ
ЅэЅУЅН ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅъЅМЅыЅєЅЁХЊАЬУжЄХЄБЄЮЅяЅЄЅѓЁЃ5НЕДжЄЮЬкРНГЋЪќМАШАЙкСхЄЧЄЮОњЄЗШАЙкЄЮИхЁЂТчУЎЄЧ7ЧЏНЯРЎЁЂЅмЅШЅыЄЧЄтКЧФу7ЧЏПВЄЋЄЛЄЦЄЋЄщЅъЅъЁМЅЙЁЃ
ЄНЄЗЄЦКЃВѓПЗЄПЄЫХўУхЄЗЄПЅяЅЄЅѓ
ЁћЅэЅУЅНЁІЅжЅьЅА2007ЧЏ
ЁћЅэЅУЅНЁІЅыЅЄЁМЅЮ2005ЧЏ
ЄЧЄЙЁЃ
ЄГЄСЄщЄЯЄоЄППВЄЋЄЛЄЦГкЄЗЄпЄПЄЄЄЧЄЙЄЭ
АЪВМРИЛКМдО№Ъѓ
ЅЙЅэЅєЅЇЅЫЅЂЄШЄЮЙёЖЩеЖсЁЂЅЂЅЩЅъЅЂГЄЄШЅИЅхЅъЅЂЅѓЅЂЅыЅзЅЙЄЮУцДжЄЫАЬУжЄЙЄыЅГЅУЅъЅЊЄЮЕжЮЭУЯТгЁЂЅДЅъЅФЅЃЅЂЛдЙйГАЄЮЅЊЅЙЅщЁМЅєЅЃЅЂЄЫЄЂЄыЅяЅЄЅЪЅъЁМЁЃЅЊЅЙЅщЁМЅєЅЃЅЂЄЯЁЂЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮТОЄЫЄтЅщЅЧЅЃЅГЅѓЁЂЅЋЅЙЅЦЅУЅщЁМЅРЄфЅРЁМЅъЅЊЁІЅзЅъЅѓЅСЅУЅСЄШЄЄЄУЄПЅЄЅПЅъЅЂЄЮЅЪЅСЅхЅщЅыЅяЅЄЅѓГІЄђТхЩНЄЙЄыяЃЁЙЄПЄыТЄЄъМъЄПЄСЄЌЬЉНИЄЙЄыЅОЁМЅѓЄЧЁЂШщЄДЄШЄЮШАЙкЄђЛмЄЗЄПЧђЅяЅЄЅѓЄђРЄГІУцЄЫЙЄсЄППЬИЛУЯЄШИРЄУЄЦЄтВсИРЄЧЄЯЄЂЄъЄоЄЛЄѓЁЃЄНЄЮГЫЄШЄЪЄУЄЦЄЄЄПЄЮЄЌЁЂЅЄЅПЅъЅЂЧђЅяЅЄЅѓГІЄЮЕ№ПЭЄЧЄЂЄъЁЂАЮТчЄЪЩуЄЧЄтЄЂЄыЁЂЅшЅЙЅГ ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЧЄЙЁЃ
1901ЧЏЄЫИНХіМчЅшЅЙЅГЄЮСНСФЩуЄЌЁЂ2.5haЄЮХкУЯЄШВШЄђЙиЦўЄЙЄыЄГЄШЄЧЧРОьЄШЄЗЄЦЄЮГшЦАЄђГЋЛЯЄЗЄоЄЗЄПЁЃ1980ЧЏТхЄЫЦўЄъЧРОьЄђАњЄЗбЄЄЄРЅшЅЙЅГЄЯЁЂЁжТПЄЋЄэЄІЁЂЮЩЄЋЄэЄІЁзЄЌЅтЅУЅШЁМЄРЄУЄП80ЧЏТхЁС90ЧЏТхНщЄсКЂЄоЄЧЄЯЁЂКЧПЗЕЛНбЄШИЦЄаЄьЄыЄтЄЮЄЯЄвЄШФЬЄъЛюЄЗЁЂХіЛўЄЮЮЎЙдЄЫТЇЄУЄПИНТхХЊЄЪЅЙЅПЅЄЅыЄЮЅяЅЄЅѓЄђТЄЄъЁЂХіНщЄЋЄщЙтЩОВСЄђМѕЄБЄЦЄЄЄоЄЗЄПЁЃЄЗЄЋЄЗЁЂРЄДжЄЧЄЮЩОВСЄШМЋПШЄЌФЩЄЄЕсЄсЄыЄтЄЮЄШЄЮДжЄЫаЊЮЅЄЌЄЂЄыЄГЄШЄЫЕЄЄХЄЄЄПЅшЅЙЅГЄЯЁЂ90ЧЏТхУцЄДЄэЄЋЄщЁЂУЯАшЄЮХСХ§ЄфЅяЅЄЅѓТЄЄъЄЮИЖХРЄЫЬсЄыЄшЄІЄЪЪ§ИўЄЫТЩЄђРкЄъЁЂЅЙЅЦЅѓЅьЅЙЅПЅѓЅЏЄфЅаЅъЅУЅЏЄЪЄЩЄЮОњТЄРпШїЄђНшЪЌЁЂ"5000ЧЏАЪОхЄЫЄяЄПЄУЄЦТГЄЄЄЦЄЄПЅяЅЄЅѓОњТЄЄЮХСХ§/ЮђЛЫЄЌЁЂЄПЄУЄПННПєЧЏЄЧНёЄДЙЄЈЄщЄьЄыЄГЄШЄЪЄЩЄЂЄУЄЦЄЯЄЪЄщЄЪЄЄ"ЄШЄЮЛзЄЄЄЋЄщЁЂШЊЄЧЄтЅЛЅщЁМЄЧЄтЄшЄъМЋСГЄЪЅЂЅзЅэЁМЅСЄђСЊТђЄЙЄыЄшЄІЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃ
ИНКпЬѓ15ЅиЅЏЅПЁМЅыЄЂЄыЅжЅЩЅІШЊЄЧЄЯЁЂМЋСГДФЖЄЫЗЩАеЄђЪЇЄУЄПЧРЖШЄђПДГнЄБЁЂЧРЬєЄфВНГиШюЮСЄЯАьРкЛШЭбЄЛЄКЁЂЩдЙЬЕЏЄЫЄшЄыС№РИКЯЧнЄђЙдЄУЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ2012ЧЏЄЮМ§ГЯФОИхЄЫЅНЁМЅєЅЃЅЫЅчЅѓЁЂЅдЅЮ ЅАЅъЁМЅИЅчЁЂЅЗЅуЅыЅЩЅЭЁЂЅъЁМЅЙЅъЅѓЅАЄђАњЄШДЄЁЂ2013ЧЏАЪЙпЄЯХкУхЩЪМяЄЧЄЂЄыЅъЅмЅУЅщ ЅИЅуЅУЅщЄЮЄпЄђКЯЧнЁЃМЋСГДФЖЄЮЅаЅщЅѓЅЙЄђМшЄъЬсЄЙЄПЄсЁЂШЊЄЫЄЯУгЄтКюЄъЁЂШљРИЪЊЄфУюЁЂФЛЄПЄСЄЮРИТЉУЯЄЫЄтЄЪЄУЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
УЯВМЄЫЄЂЄыЅЛЅщЁМЄЧЄЯЁЂУЯУцЄЫЫфЄсЄПЅИЅчЁМЅИЅЂРНЄЮЅЂЅѓЅеЅЉЅщ(СЧОЦЄЄЮсБ)ЄЧЬѓШОЧЏДжШщЄДЄШЄЮШАЙкЄШНЯРЎЄђЙдЄЄЁЂАЕКёИхКЦЄгЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄиЄШЬсЄЗШОЧЏДжНЯРЎЁЂЄНЄЮИхЁЂГпЄЮТчУЎЄЧЬѓ6ЧЏДжНЯРЎЄЕЄЛЄЦЩгЕЭЄсЄђЙдЄЄЁЂКЧУЛЄЧЄтМ§ГЯЧЏЄЋЄщ7ЧЏИхЄШЄЄЄІЧЏЗюЄђЗаЄЦЅъЅъЁМЅЙЄЕЄЛЄоЄЙЁЃЅЛЅщЁМЄЮОњТЄРпШїЄЧХХЮЯЄђЛШЭбЄЙЄыЄтЄЮЄЯЅзЅьЅЙЕЁЁЂЅнЅѓЅзЁЂЅмЅШЅъЅѓЅАЕЁЄЮЄпЄЧЁЂЩЌЭзКЧОЎИТЄЮЅЈЅЭЅыЅЎЁМЄЧОњТЄЄЋЄщЅмЅШЅъЅѓЅАЄоЄЧЄђЙдЄЄЁЂИНКпЄЯФЙНїЄЮЅоЅЦЅЄЅЂЄЌЅшЅЙЅГЄђМъХСЄІЄЋЄПЄСЄЧЁЂЅяЅЄЅЪЅъЁМЄЮБПБФЄђЙдЄУЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
АЪВМСАВѓЄДОвВ№ЪИ
ЅАЅщЅєЅЭЅы
ЅъЅмЅУЅщ2011ЧЏЄЧЄЙЁЊЁЊЁЊ
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭАЗЄЄЄЮЅеЅъЅІЁМЅъЄЮНХФУ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЧЄЙЁЃ
ЄГЄЮЄиЄѓЄЮЅьЅйЅыЄЮЅяЅЄЅѓЄШЄЪЄыЄШ
ХіХЙЄЮЄДОвВ№БОЁЙЄЧЄЩЄІЄШЄЪЄыТЄЄъМъЄЕЄѓЄЧЄЯЄЪЄЏ
ЛдОьЄЮЄІЄЭЄъЄЮУцЄЫ
ХіХЙЄтЄСЄчЄУЄШЄРЄБКЎЄЖЄщЄЛЄЦЄЄЄПЄРЄЄЄЦЄЄЄы
АЗЄяЄЕЄЛЄЦЄтЄщЄУЄЦЄЄЄы
ЄНЄѓЄЪЅьЅйЅыЄШЄЪЄъЄоЄЙЄЌ
ЛфЄтОмЄЗЄЏЄЯУЮЄъЄоЄЛЄѓЄЌ
КЃЄоЄЧЄтфўЭОЖЪРоЄЂЄУЄЦЄЮКЃЄЌЄЂЄыТЄЄъМъЄЕЄѓЄЮЄшЄІЄЧ
ЄШЄЪЄыЄШ
КЃИхЄт
ВСГЪЬЬЄтДоЄсЄЩЄІЄЪЄУЄЦЄЄЄЏЄЮЄЋ
ЄЩЄІЄЄЄУЄПЪ§ИўРЄиЄШПЪЄѓЄЧЄЄЄЏЄЮЄЋ
СДЄЏЄяЄЋЄщЄЪЄЄ
ЄРЄЋЄщЄГЄНКЃЄЂЄыЕЎНХЄЪЅяЅЄЅѓЄђТчЛіЄЫЄЗЄЦЄЄЄЏЄГЄШЄтЩЌЭзЄШ
ЛзЄЈЄыЅяЅЄЅѓЄРЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
ХіХЙЄЮЄЊМшАњЄЮУцЄЧЄт
МЋСГЧЩЅяЅЄЅѓБОЁЙДиЗИЄЪЄЏ
АІЄЕЄьЄы
ДЖЦАЭПЄЈЄыЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓ
КЃВѓХўУхЄЯ
ЅгЅѓЅЦЁМЅИПЪЄп
ЅъЅмЅУЅщЄЮ2011ЧЏЄШЄЪЄъЄоЄЙЁЃ
КЃВѓ2011ЧЏЄтзИЕщЄЮЅъЅмЅУЅщЄШЄЮЄГЄШЄЧ
ЅЂЅыЅГЁМЅыХйПє15,5%
ЄЄЄФЄтЄЮЄшЄІЄЪЧГЄЈЄыЭЭЄЪЅЈЅЅЙДЖЧЛЬЉЄЪЛнЬЃ
ЙлЪЊХЊЄЪЅпЅЭЅщЅыЄтЄНЄЮЅЈЅЅЙЄЫЄоЄШЄяЄъЄФЄЏЄшЄІЄЪЧЛЬЉЄЕЄЧ
ЅаЅщЅѓЅЙЄЂЄыЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЬЅЮЯ
ДЖЄИЄЦЄЄЄПЄРЄБЄыЄЮЄЧЄЯЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
АЪВМ2010ЧЏЄДОвВ№ЪИ
ЅАЅщЅєЅЭЅы
ЅъЅмЅУЅщ2010ЧЏЄЧЄЙЁЊ
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄЮ
ЅеЅъЅІЁМЅъЄЮЕ№ПЭ
ТОЄђЄНЄѓЄЪЄЫУЮЄщЄЪЄЄЄЪЄЌЄщЄт
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄЮЄШЄГЄэЄЫНИЄоЄъЄЙЄЎЄЦЄЄЄыЄЮЄЧЄЯЁЉЄШЛзЄІЄлЄЩЄЧЄЙЄЌ
ЄНЄьЄРЄБЄЮЕсПДЮЯЄЌЄЂЄыЄРЄцЄЈЄЋЄЪЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
ЄНЄЗЄЦЄНЄЮУцЄЧЄт
ЄЪЄѓЄШЄЄЄЄЄоЄЗЄчЄІЄЋ
ЅЪЅСЅхЁМЅыАьЪеХнЄЮЪ§АЪГАЄЫЄтЛйЛ§ЄЕЄьЄыЅяЅЄЅѓЄЧЄтЄЂЄы
ЅАЅщЅєЅЭЅы
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄЧЄЮЄЊМшАЗЄЄЄШЄЪЄъ
ХіХЙЄтЄПЄоЄЫЄЊМшАЗЄЄЄЧЄЄыЄшЄІЄЫЄЪЄъЄоЄЗЄПЄЌ
КЧЖсЄЮЗЙИўИЋЄЦЄЄЄыЄШ
ЦўВйЫмПєЄтОЏЄЪЄЄЄШЄЄтЄЂЄьЄа
ВСГЪОхОКИЗЄЗЄЄЄтЄЮЄтЄЂЄУЄПЄъЄШ
ЄГЄьЄРЄБУэЬмНИЄсЄыТЄЄъМъЄРЄЋЄщЄГЄН
ЄоЄПЙдЦАЄфИРЦАЄтЛЩЗуХЊЄРЄЋЄщЄГЄН
ЪбВНЄтТчЄЄЄЄЮЄЋЄЪЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
КЃВѓЅъЅмЅУЅщ2010ЧЏ
КЃВѓЄЯАћЄѓЄЧЄЊЄъЄоЄЛЄѓЄЮЄЧ
САВѓАћЄѓЄРЅъЅмЅУЅщЄЮАѕОнЄЧЄЙЄЌ
ЅъЅмЅУЅщ08ЄЮДЖЄИЄЧЄЙЁЃ
ЅъЅмЅУЅщЅИЅуЅУЅщЄЮ2008ЧЏАћЄпЄоЄЗЄП
РЕФОНщЦќЄЮУЪГЌЄЧ
ЄНЄЮИЗЄЗЄЕЄШЄЄЄІЄЋЅЙЅШЅЄЅУЅЏЄЕЅЏЁМЅыЄШЄЄЄІЄшЄъЄЯ
РкЄъЮЉЄУЄПЛГЄШЄЋИЗЄЗЄЕЄЌЄЂЄыЅяЅЄЅѓЄШДЖЄИЄЦ
08ЄЪЄЋЄЪЄЋТчЪбЄЋЄЪЄШЛзЄЄЄЄф
ЄГЄьЄЌЦѓЦќЬмЛАЦќЬмЄШЄЩЄѓЄЩЄѓФДЯТЄЗЄЦЮЩЄЄЪ§ИўЄиЄШИўЄЋЄУЄЦЄЄЄЏЅяЅЄЅѓ
ПЇЄЯЅЊЅьЅѓЅИУуЗЯЄЧЄтЅЏЅъЅЂЁМЄЧ
ЄГЄЮПЇФДЄтЦѓЦќЬмЛАЦќЬмЄШЄшЄъУуПЇЄГЄВУуЗЯС§ЄЗЄЦЄЄЄЏ
С§ЄЗЄЦЄЄЄЏЄШЄшЄъПЇЄЌНаЄЦЄЏЄыЄЪЄѓЄЋЮЩЄЕЄЌНаЄЦЄЏЄыЩдЛзЕФЄЪЅяЅЄЅѓ
ЅЊЅьЅѓЅИВЬШщДЖЄЂЄъ
ДЛЕЬЅЗЅэЅУЅзФвЄБЅЗЅъЅЂЅыЄЕЄЂЄъЅЩЅщЅЄЄЪЄЮЄЫЬЊДЖЄтЄЂЄы
ЖьЬЃЄтОЏЁЙЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄЮНТЁЉГСНТЄЮЄшЄІЄЪЅПЅѓЅЫЅѓ
ЄЪЄЋЄЪЄЋЄЫЙХЧЩЄЪДЖЄИЄЧЄЗЄПЄЌ
АћЄрЄДЄШЄЫОЏЄЗЄКЄФЬЅЮЯЄђВђЪќЄЕЄЛЄЦЄЄЄЏЄшЄІЄЪ
ЦѓЦќЬмАЪЙпВЬМТЄЮЅЫЅхЅЂЅѓЅЙЄтНРЄщЄЋЄЏЅЩЅщЅЄЄЕЄЯЄЂЄъЄЪЄЌЄщЄт
ЬЉХйДЖЄфПМЄпЄЯС§ЄЗЄЦЄЄЄЏЅПЅѓЅЫЅѓЄЮНТЄпЄЪЄЩЄтЭЯЄБЙўЄѓЄЧФДЯТЄЗЄЦЄЄЄЏЭЭЄЌДЖЄИЄщЄьЄоЄЙЁЃ
ЅрЅѓЅрЅѓЄШЄЗЄПЬРЄыЄЄЖЏЄЕЄфТРЄЕЄЯЬЕЄЏЄШЄт
ЦтЪёЄЙЄыЅЈЅЭЅыЅЎЁМЄЪЄЩЄЯСЧРВЄщЄЗЄЏ
ЅЗЅъЅЂЅЙЄЪПМЄп
ЅпЅЭЅщЅыДЖЄЪЄЩЄЯЄшЄъ08ЄЮЄлЄІЄЌДЖЄИЄщЄьЄоЄЙЄЗ
ИМПЭМѕЄБЄЙЄыЄоЄРРшЄНЄЗЄЦЄЕЄщЄЫБќЄЌЄЂЄъЄНЄІЄЪЕЄЄЫЄЪЄыЅяЅЄЅѓ
ЄНЄѓЄЪЕЄЄЌЄЄЄПЄЗЄоЄЙЁЃ
ЅЂЅыЅГЁМЅыХйПєЄЯ14,5%ЁЊ
АЪВМСАВѓЄДОвВ№ЪИ
ОзЗтЄЮЅАЅщЅєЅЭЅыЄЧЄЙЁЊ
ШѓОяЄЫЕЄЄЫЄЪЄУЄЦЄЄЄПЄтЄЮЄЮЄФЄЪЄЌЄщЄЪЄЋЄУЄПТЄЄъМъЄЧ
ЄНЄьЄђЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄЌЗвЄЄЄЧЄЏЄРЄЕЄУЄП
ЄНЄѓЄЪЅяЅЄЅѓ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЧЄЙЁЃ
ЅЄЅйЅѓЅШЄЧАћЄѓЄРЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓЄЫЄЪЄЋЄЪЄЋЄЫОзЗтЄЧЄЗЄПЄЌ
ХіХЙЄЊМшАњЄЗЄЦЄЄЄыАћПЉХЙЭЭЄЮЄЊЯУЄЧ
ЄГЄЮЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓ
ЄГЄЮЅяЅЄЅѓЄРЄУЄПЄщ
ЄГЄьЄРЄБЄЮТаВСЪЇЄУЄЦЄЧЄтАћЄпЄПЄЄЅяЅЄЅѓ
ЄНЄѓЄЪЯУЄђЄЊЪЙЄЄЗЄоЄЗЄПЁЃ
ЄЗЄЋЄтЄНЄЮЄЊЪ§ЄЯЅжЅыЅДЁМЅЫЅхЄЪЄЩУцПДЄЫАћЄоЄьЄЦЄЄЄыЄЋЄПЄРЄУЄПЄШ
ЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
ЄПЄРЬУОњЅяЅЄЅѓЙЄЏАћЄѓЄЧЄЊЄщЄьЄыЄшЄІЄЧ
ЄНЄЮЪ§ЄђЄЗЄЦ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓЄЯЄНЄІЄЄЄУЄПЮЉЄСАЬУжЄЫЄЂЄыЅяЅЄЅѓЄРЄШЄЋЄЧ
ЄГЄьЄРЄБЄЮЄЩЄГЄоЄЧЄтЄГЄРЄяЄъШДЄЄЄПМЋСГЄЪЅяЅЄЅѓЄЧЄЂЄъЄЪЄЌЄщ
ЄГЄЮЄЂЄыАеЬЃЪбЄяЄщЄЬЛбЄђБЧЄЗНаЄЙЅяЅЄЅѓ
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄЮЪИОЯЄЧЄт
ЮЩЄЏЬОСАЄЌЄЂЄЌЄыЄЮЄЧЄЙЄЌ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЄШЅєЅЉЅЩЅдЁМЅєЅЇЅУЅФ
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄЋЄщЄЙЄыЄШ
ТЄЄъНаЄЙЅяЅЄЅѓЄЯЛїЄЦЄтЛїЄФЄЋЄЪЄЄЄЧЄЙЄЌЁІЁІЁІЄШЄЂЄъЄоЄЙЄЌ
ЄЪЄѓЄШЄЄЄІЄЋ
ОяЄЫЪбЄяЄщЄЬЩдЪбЄЮЬЅЮЯ
ЄНЄЗЄЦФЩЕсЄЗЄІЄыЄНЄЮРшЄЮРшЄђЕсЄсЄцЄЏУцЄЫЄПЄЩЄъУхЄЏРЄГІДбЄЂЄыЅяЅЄЅѓ
ЄГЄЮЄиЄѓЄЩЄГЄЋЖІФЬЄЗЄЦЄЄЄыЄшЄІЄЪЕЄЄтУзЄЗЄоЄЙЁЃ
ЅяЅЄЅѓЄЯАуЄЈЄЩЄт
ЖЫЄсЄцЄЏУцЄЫЦБЄИЪ§ИўЄиЄШИўЄЏЩєЪЌЄтЄЂЄыЄшЄІЄЧ
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄЮЄЊЯУ
ЗЧКмЄЕЄЛЄЦЄЄЄПЄРЄЄоЄЙЁЃ
ЅшЅЙЅГЄШЅбЅЊЅэЁЂТЄЄъНаЄЙЅяЅЄЅѓЄЯЛїЄЦЄтЛїЄФЄЋЄЪЄЄЄЧЄЙЄЌЁЂШрЄщ2ПЭЄлЄЩЅЙЅШЅЄЅУЅЏЄЧНЊЛЯАьДгЄЗЄП(ЅЪЅСЅхЅщЅы)ЅяЅЄЅѓДбЁЂ(ЅЪЅСЅхЅщЅы)ЅяЅЄЅѓЦЛЄђДгЄЄЄЦЄЄЄыТЄЄъМъЄЯЄЄЄЪЄЄЕЄЄЌЄЗЄоЄЙЁЃВПХРЄЋОнФЇХЊЄЪЄШЄГЄэЄђЮѓЕѓЄЗЄоЄЙЄШЁЂ
ЁІМЋСГДФЖЄЫЗЩАеЄђЪЇЄУЄПЧРЖШЄђПДГнЄБЁЂЅЛЅщЁМЄЧЄЯЅвЅШЄЮЅЈЅДЄђМЮЄЦЁЂЅжЅЩЅІЁЂЅяЅЄЅѓЁЂЙкЪьЄПЄСЄЮРМЄЫМЊЄђЗЙЄБЄыЄшЄІЄЪОњТЄЄђПДГнЄБЁЂЄНЄьЄщЄЌЕяПДУЯЄЮЮЩЄЄДФЖЄђСЯНаЄЙЄыЄГЄШЄЫПДЄђКеЄЏЁЃ
ЁІШАЙкЁѕНЯРЎЄЫЄЯЁЂЅЪЅСЅхЅщЅыЄЪЅоЅЦЅъЅЂЅыЄЧЄЂЄъЅЙЅЦЅѓЅьЅЙЄЮЄшЄІЄЫТгХХЄЗЄфЄЙЄЄ(ЁсЭЦДяЦтЄЮБеТЮЄЌХХЛвЅьЅйЅыЄЧЫНЄьЄфЄЙЄЏЄЪЄы)СЧКрЄЧЄЯЄЪЄЄЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄШЬкУЎЄЮЄпЄђЛШЭбЁЃ
ЁІЅЪЅСЅхЅщЅыЄЪЅяЅЄЅѓЄђМТИНЄЙЄыЄПЄсЄЫЁЂРаЬ§ВНГиЅЈЅЭЅыЅЎЁМЄЪЄЩЄЫТхЩНЄЕЄьЄыЁЂДФЖЄЫЩщВйЄђЭПЄЈЄыЄтЄЮЄЫЖЫУМЄЫАЭТИЄЗЄЦЄЄЄЦЄЯЫмЫіХОХнЁЂЩЌЭзКЧОЎИТЄЮЅЈЅЭЅыЅЎЁМЄЧОњТЄЄЋЄщЅмЅШЅъЅѓЅАЄоЄЧЄђЙдЄІ(ЅЋЁМЅМЅГЅъЁМЅЫЄЮЅэЅьЅѓЅФЅЉЧюЛЮЄЌИРЄІЄШЄГЄэЄЮЅЋЁМЅмЅѓЅеЅУЅШЅзЅъЅѓЅШ)ЁЃЮОПЭЄЮЅЛЅщЁМЄШЄтУЯВМЄЫЄЂЄъЁЂЖѕФДЄЪЄЩЄЌЩЌЭзЄЮЄЪЄЄДФЖЄЧЁЂОВЄтЪЩЄтЅГЅѓЅЏЅъЁМЅШЄЧАЯЄУЄЦЄЄЄЪЄЄЄПЄсЁЂЖѕЕЄЄЯОяЄЫТаЮЎЄЗЁЂФДМОЄЮЩЌЭзЄтЄЪЄЄЁЃЅшЅЙЅГЄЮЅЛЅщЁМЄЮОњТЄРпШїЄЧХХЮЯЄђЛШЭбЄЙЄыЄтЄЮЄЯЁЂКЃЄфЅзЅьЅЙЕЁЁЂЅнЅѓЅзЁЂЅмЅШЅъЅѓЅАЕЁЄЮЄпЄЧ(2017ЧЏЄЋЄщНќЙМЄђЄЛЄКЄЫСДЫМШАЙкЄђМТСЉ)ЁЂЖВЄщЄЏЅбЅЊЅэЄЯЄГЄьЄЫНќЙМЕЁЄЌВУЄяЄыФјХйЄЋЄШЁФЁЃ
ЄШЄЮЄГЄШ
КйЄЋЄЄЗаАоЄЯЄяЄЋЄщЄЪЄЄЄШЄГЄэТПЄЄЄЮЄЧЄЙЄЌ
ЄГЄЮЅшЅЙЅГЁІЅАЅщЅєЅЭЅы
ЄГЄЮЅеЅъЅІЁМЅъЄЮЄлЄЋЄЮРИЛКМдЄШЄЮДиЗИЄЂЄѓЄоЄъЮЩЄЏЄЪЄЋЄУЄПЄшЄІЄЧЄЙЄЌ
ЄНЄьЄђЭЯЄЋЄЗ
ЅщЅЧЅЃЅГЅѓЁЂЅЋЅЙЅЦЅУЅщЁМЅРЁЂЅбЅЊЅэ ЅєЅЉЅЩЅдЁМЅєЅЇЅУЅФЁЂЅрЅьЅСЅЫЅУЅЏЁЂЅРЁМЅъЅЊ ЅзЅъЅѓЅСЅУЅСЁЂЅжЅьЅУЅЕЅѓЄЌНИЄІПЉЛіВёЄЫЅшЅЙЅГЄтКЎЄЖЄыЄшЄІЄЫЄЪЄУЄПЄШЄЋЄЧ
ЄЋЄЪЄъЄЙЄДЄЄЄГЄШЄЮЄшЄІЄЧЄЙЁЃ
ЄЕЄщЄЪЄыЅеЅъЅІЁМЅъЄЮВПЄЋПЪВНЄЌКЃИхЄЂЄыЄшЄІЄЫЛзЄЈЄЦЄЪЄъЄоЄЛЄѓЁЃ
ЄШЄЄЄІЄГЄШЄЧКЃВѓЄЮЅАЅщЅєЅЭЅыЄЧЄЙЄЌ
КЦЦўВйЄЧ
ЅгЅЂЅѓЅГЁІЅжЅьЅА2007ЧЏ
ЅгЅѓЅЦЁМЅИЄЮБЦЖСЄтЄЂЄъЅЄЅйЅѓЅШЄЧАћЄѓЄРЛўЄт
ЄГЄЮЅяЅЄЅѓЄЮЬЅЮЯЄЌСЧРВЄщЄЗЄЏХСЄяЄыЄяЄЋЄъЄфЄЙЄЄ
НщЄсЄЦАћЄѓЄРЅАЅщЅєЅЭЅыЄЌЄГЄЮЅяЅЄЅѓЄЧЮЩЄЋЄУЄПЄНЄѓЄЪЕЄЄЌЄЄЄПЄЗЄоЄЙЄЌ
ЅяЅЄЅѓЄЮЅЦЅѓЅЗЅчЅѓЄШЄЋЬЉХйДЖ
ЅъЅЂЅыЄЪЅеЅыЁМЅФЄНЄьЄЌЙтЕЎЄЪЄтЄЮЄиЄШОКВкЄЗЄЦ
ЄяЄЋЄъЄфЄЙЄЏЄЙЄДЄЄЅяЅЄЅѓЄШДЖЄИЄыЄтЄЮ
ЄНЄьЄтЄГЄЮ07ЄЮЮЩЄЄЄШЄГЄэЄЮЄшЄІЄЧ
ЄяЄЋЄъЄфЄЙЄЏРЈЄЄЅяЅЄЅѓЄШДЖЄИЄыЄНЄѓЄЪЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓЄЧЄЂЄъЄоЄЗЄПЁЃ
ЄНЄЗЄЦКЃВѓПЗЅгЅѓЅЦЁМЅИЄЮ
ЅгЅЂЅѓЅГЁІЅжЅьЅА2008ЧЏ
БЋЄЌЄСЄРЄУЄП08ЄШЄЮЄГЄШЄЧ
ФЬОяЄРЄШЄНЄЮЪЌЧіЄсЄШЄЋМхЄЏЄЪЄъЄНЄІЄЪЄШЄГЄэ
МТЄЯЅЂЅыЅГЁМЅыХйПєЄЌЙтЄЄЁЊЄШЄЮЄГЄШ
ЄНЄЮИЖАјЄШЄЗЄЦЄЂЄыЄЮЄЌЕЎЩхЄШЄЮЄГЄШ
ПхЪЌШєЄаЄЗЄЦЄшЄъЖХНЬЄЗЄПЅЈЅЅЙЄиЄШЄНЄЮЭзСЧЄЌЄЂЄъ
ЅЂЅыЅГЁМЅыХйПєЄЌ07ЄшЄъЄтЙтЄЄЄтЄЮЄШЄЪЄУЄЦЄЄЄыЄшЄІЄЧЄЙЁЃ
ЄПЄРЅяЅЄЅѓЄЮЅЅуЅщЅЏЅПЁМЄЯЄфЄЯЄъЪбЄяЄъ
07ЄЌЅрЅѓЅрЅѓЗЯЄЮЦљДЖЄЂЄыЅяЅЄЅѓЄЫТаЄЗЄЦ
08ЄЯЅЏЁМЅыЄЧЄфЄфЦтИўХЊ
ЄЧЄтШыЄсЄПЄыЅнЅЦЅѓЅЗЅуЅыЄЯРЈЄЄЄтЄЮЄЂЄъЄоЄЙЁЃ
КЃВѓЄтЄІАьЄФЄЮ2008ЧЏЅяЅЄЅѓ
ЅъЅмЅУЅщЅИЅуЅУЅщЄЮ2008ЧЏАћЄпЄоЄЗЄП
РЕФОНщЦќЄЮУЪГЌЄЧ
ЄНЄЮИЗЄЗЄЕЄШЄЄЄІЄЋЅЙЅШЅЄЅУЅЏЄЕЅЏЁМЅыЄШЄЄЄІЄшЄъЄЯ
РкЄъЮЉЄУЄПЛГЄШЄЋИЗЄЗЄЕЄЌЄЂЄыЅяЅЄЅѓЄШДЖЄИЄЦ
08ЄЪЄЋЄЪЄЋТчЪбЄЋЄЪЄШЛзЄЄЄЄф
ЄГЄьЄЌЦѓЦќЬмЛАЦќЬмЄШЄЩЄѓЄЩЄѓФДЯТЄЗЄЦЮЩЄЄЪ§ИўЄиЄШИўЄЋЄУЄЦЄЄЄЏЅяЅЄЅѓ
ПЇЄЯЅЊЅьЅѓЅИУуЗЯЄЧЄтЅЏЅъЅЂЁМЄЧ
ЄГЄЮПЇФДЄтЦѓЦќЬмЛАЦќЬмЄШЄшЄъУуПЇЄГЄВУуЗЯС§ЄЗЄЦЄЄЄЏ
С§ЄЗЄЦЄЄЄЏЄШЄшЄъПЇЄЌНаЄЦЄЏЄыЄЪЄѓЄЋЮЩЄЕЄЌНаЄЦЄЏЄыЩдЛзЕФЄЪЅяЅЄЅѓ
ЅЊЅьЅѓЅИВЬШщДЖЄЂЄъ
ДЛЕЬЅЗЅэЅУЅзФвЄБЅЗЅъЅЂЅыЄЕЄЂЄъЅЩЅщЅЄЄЪЄЮЄЫЬЊДЖЄтЄЂЄы
ЖьЬЃЄтОЏЁЙЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄЮНТЁЉГСНТЄЮЄшЄІЄЪЅПЅѓЅЫЅѓ
ЄЪЄЋЄЪЄЋЄЫЙХЧЩЄЪДЖЄИЄЧЄЗЄПЄЌ
АћЄрЄДЄШЄЫОЏЄЗЄКЄФЬЅЮЯЄђВђЪќЄЕЄЛЄЦЄЄЄЏЄшЄІЄЪ
ЦѓЦќЬмАЪЙпВЬМТЄЮЅЫЅхЅЂЅѓЅЙЄтНРЄщЄЋЄЏЅЩЅщЅЄЄЕЄЯЄЂЄъЄЪЄЌЄщЄт
ЬЉХйДЖЄфПМЄпЄЯС§ЄЗЄЦЄЄЄЏЅПЅѓЅЫЅѓЄЮНТЄпЄЪЄЩЄтЭЯЄБЙўЄѓЄЧФДЯТЄЗЄЦЄЄЄЏЭЭЄЌДЖЄИЄщЄьЄоЄЙЁЃ
ЅрЅѓЅрЅѓЄШЄЗЄПЬРЄыЄЄЖЏЄЕЄфТРЄЕЄЯЬЕЄЏЄШЄт
ЦтЪёЄЙЄыЅЈЅЭЅыЅЎЁМЄЪЄЩЄЯСЧРВЄщЄЗЄЏ
ЅЗЅъЅЂЅЙЄЪПМЄп
ЅпЅЭЅщЅыДЖЄЪЄЩЄЯЄшЄъ08ЄЮЄлЄІЄЌДЖЄИЄщЄьЄоЄЙЄЗ
ИМПЭМѕЄБЄЙЄыЄоЄРРшЄНЄЗЄЦЄЕЄщЄЫБќЄЌЄЂЄъЄНЄІЄЪЕЄЄЫЄЪЄыЅяЅЄЅѓ
ЄНЄѓЄЪЕЄЄЌЄЄЄПЄЗЄоЄЙЁЃ
ЅЂЅыЅГЁМЅыХйПєЄЯ14,5%ЁЊ
ЄНЄЗЄЦКЧИхЄЯ
ЅяЅЄЅѓЄЧЄЯЄЪЄЏ
ЅГЅУЅб2ЕгЅЛЅУЅШЄШЄЄЄІЄГЄШЄЧ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓЄЮЄПЄсЄЫЄФЄЏЄщЄьЄПЦУЪЬЅАЅщЅЙЄЧЄЙЁЃ
ЕгЄЮЄЪЄЄЅПЅЄЅзЄЧ
ЦѓЫмЄЮЛиЄЧЛйЄЈЄыЄшЄІЄЮЄиЄГЄпЄЌЄЂЄъ
ЅАЅщЅЙЄЮЭЦЮЬХЊЄЫЄЯЄБЄУЄГЄІЦўЄы
ЄПЄжЄѓЅщЅЧЅЃЅГЅѓЅАЅщЅЙЄШЦБХљФјХйЄЮЭЦЮЬЦўЄы
ТчЄЄЕЄЂЄыЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
ЅЦЁМЅжЅыЄЫУжЄЄЄПЄЕЄЄЄЮАТФъДЖЄтЄЂЄъ
ЅАЅщЅЙЄЮППЄѓУцЄНЄГЄЫЄт
ДнЄпЄђТгЄгЄПЦЭЕЏЄЌЄЂЄъ
ЄНЄьЄщЄтЙЭЄЈЄщЄьЄПЄтЄЮЄЧЅяЅЄЅѓЄЌЖѕЕЄЄШПЈЄьЄыЄПЄсЄЮВПЄЋЄШЄЪЄУЄЦЄЄЄыЄЮЄЧЄЯЄШ
ЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
ЅщЅЧЅЃЅГЅѓЅАЅщЅЙЦБЭЭЄЫ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅГЅУЅбЄт
ТОЄЮМЋСГЧЩЅяЅЄЅѓАћЄрЄЮЄЫЄтНХЪѕЄЗЄНЄІЄЪДЖЄИЄЧЄЙЁЃ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЅАЅщЅЙ
ЅГЅУЅбЄЯ2ЕгЅЛЅУЅШЄЧЄЮШЮЧфЄШЄЪЄъЄоЄЙЁЃ
АЪВМ2007ЧЏЄДОвВ№ЪИ
ЕзЄЗЄжЄъЄЫЖНЪГГаЄЈЄыЅяЅЄЅѓ
ЅАЅщЅєЅЭЅыЄЧЄЙЁЃ
ЅАЅщЅєЅЭЅыАьХйЄЯЪЙЄЄЄПЄГЄШЄЂЄыЅяЅЄЅѓ
ТЄЄъМъ
ЅАЅщЅєЅЪЁМЄШЄЋ
ЅшЅЙЅГЁІЅАЅщЅєЅЭЅы
ЄШЄЋ
ЅяЅЄЅѓМЋТЮЄЌХіХЙЄШЄЯЪЬЄЪЮЎФЬЄШЄЄЄІЄЋМЁИЕЄЧ
ШєЄгИђЄУЄЦЄЄЄПЄЮЄЋЄт
ЄЧ
НаВёЄІЄГЄШЄЯЬЕЄЋЄУЄПЄЮЄЧЄЙЄЌ
ЄЩЄГЄЋЄЧЄНЄЮТИКпЄРЄБЄЌТчЄЄЏЄЪЄъЄНЄЗЄЦ
ЄШЄЫЄЋЄЏЄЙЄДЄЄЅяЅЄЅѓЄЪЄѓЄРЄэЄІЄЋЁІЁІЁІЄШ
ЄНЄѓЄЪДЖЄИЄЧЄЗЄПЁЃ
ЄЧЄтКЃЄЯЬЕЭ§ЄЫЄПЄЩЄъУхЄЏЄшЄъЄтЄтЄУЄШМЋСГТЮЄЧ
БПЬПХЊЄЪНаВёЄЄЄђТчЛіЄЫЄШПЪЄѓЄЧЄЄЄыЄшЄІЄЪЕЄЄЌЄЗЄоЄЙЁЃ
ЭпФЅЄУЄПЄъЬЕЭ§ЄЗЄЦЄтЮЩЄЄЄГЄШЄЯЄЪЄЄЄЮЄЧЁІЁІЁІ
ЄЧЄтЄГЄГЄЫЄЄЦЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄЌАњЄЙчЄяЄЛЄЦЄЏЄьЄПЄНЄѓЄЪДЖГаЄЧЄЙЄЭ
ЄЗЄЋЄтЄЄЄЄЪЄъЄЮНаВёЄЄЄЌ
ЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЅУЅЦЅЃЅоЁМЅЪЄЧЄЮЅАЅщЅєЅЭЅыЄЕЄѓЄЮФЙНїЅоЅЦЅЄЅЂЄЕЄѓЄЌЭшЦќЄЗЄЦ
ЄНЄГЄЧФОРмУэЄЄЄЧЄЄЄПЄРЄБЄы
ЄНЄьЄЌНщЄсЄЦЄЮЅАЅщЅєЅЭЅыЄШЄЪЄыЄЪЄѓЄЦ
СДЄЏУЮЄщЄЪЄЄЄЮЄЫ
ТИКпЄРЄБЄЌТчЄЄЏЄЪЄъЄНЄьЄЧАћЄрЁЊ
ЄНЄЗЄЦРЈЄЄЅяЅЄЅѓЄЫЁІЁІЁІ
АьХйЄШЄЄЄІЄЋЄСЄуЄѓЄШЦЌЄЮУцЄђРАЭ§ЄЗЄЪЄБЄьЄаЄЄЄБЄЪЄЄЄЮЄЧЄЙЄЌ
ЄоЄКЅЄЅПЅъЅЂЄЯЅеЅъЅІЁМЅъЄЮТЄЄъМъ
ЅГЅУЅъЅЊЄЫЄЪЄыЄшЄІЄЧ
ЬСЭЇЅщЅЧЅЃЅГЅѓ
ЄНЄЗЄЦЅщЁІЅЋЅЙЅЦЅУЅщЁМЅРЄЮЖсЄЏЄЮЄшЄІЄЧЄЙЄЭ
ЄШЄЄЄІЄЋЄГЄЮУЯАшЄЩЄІЄЪЄУЄЦЄЄЄыЄЮЄЧЄЗЄчЄІЄЭ
ЅеЅъЅІЁМЅъСДТЮЄђИЋЄЦЄт
ЄЪЄѓЄЧЄГЄѓЄЪЄЫЧЛЄЄЁСЄНЄЗЄЦЛЩЗуХЊЄЪ
ЄЕЄщЄЫЄЯЛзЮИПМЄЄЄНЄЗЄЦЄШЄѓЄЧЄтЄЪЄЄЙдЦАЮЯЄђЛ§ЄФЪ§ЁЙЄЌ
НИЄоЄУЄПЄЮЄЋЁЊЁЉ
ЩдЛзЕФЄЧЄЪЄъЄоЄЛЄѓЁЃ
ГЮМТЄЫРИЛКМдЄЩЄІЄЗЄЌЛЩЗуЄЗЙчЄУЄПЄШЄЋЄНЄѓЄЪЮђЛЫЄЌ
ЄЂЄУЄЦЄЪЄЮЄЋЄЪЄШ
ЦУЄЫЅщЅЧЅЃЅГЅѓЄШЄЯЄЋЄЪЄъЖсЄЄТИКпЄРЄУЄПЄШЄЮО№ЪѓЄЂЄыЄшЄІЄЧЄЙЁЃ
ЄНЄЗЄЦКЯЧнЄЪЄЩЄЯЅгЅЊЅэЅИЅУЅЏЁЂЅгЅЊЅЧЅЃЅЪЅп
ЄНЄЗЄЦАьШжЖУЄЄЄПЄГЄШЄЯ
ЅЄЅПЅъЅЂЄЮЅяЅЄЅѓТЄЄъЄЮЖсТхВНЄђ
ЄоЄЕЄЫЦЭЄПЪЄѓЄЧЄЄП
ЄНЄьЄщЄђЄЙЄйЄЦЛюЄЗЄЦЄЄЦ
КЧНЊХЊЄЫВПЄтВУЄЈЄКЁЂВПЄтАњЄЋЄЪЄЄЅяЅЄЅѓТЄЄъ
ЄНЄГЄиЄПЄЩЄъУхЄЄЄП
ЄНЄЗЄЦЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄЧЄЮЛХЙўЄпЄШЄЪЄУЄПЄяЄБЄЧЄЙЄЭ
ЅяЅЄЅѓТЄЄъЄЮЖсТхВН
АьЛўДќЄЯЖсТхХЊЄЪЅЙЅЦЅѓЅьЅЙЅПЅѓЅЏЄиЄШАмЙдЄЗЄНЄЮИхЄЯЅаЅъЅУЅЏЄЧЄЮШАЙкНЯРЎ
ЄНЄЮЛўТхЄНЄЮЛўТхЄЮЖсТхВНЄђПЪЄс
ЄЕЄщЄЫЄЯЄНЄЮУцЄЧСЧРВЄщЄЗЄЄЩОВСЄђЦРЄЦЄЄЄПЄШЄЄЄІЄГЄШЄЧЄЙЁЃ
ЄЗЄЋЄЗЄНЄГЄЋЄщМЋСГЄЪТЄЄъЄиЄШПЪЄоЄЪЄБЄьЄаЄЄЄБЄЪЄЄЄШ
ОЏЄЗЄКЄФЖсТхВНЄЋЄщБѓЄЖЄЋЄУЄЦЄЄЄЏЦЛЄђСЊЄѓЄРЄшЄІЄЧЄЙЁЃ
ЄНЄЗЄЦЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄиЄШЄПЄЩЄъУхЄЄЄПЄШЁІЁІЁІ
ЄНЄЮЅяЅЄЅѓЄђЅшЅЙЅГЁІЅАЅщЅєЅЭЅыЄЕЄѓЄЮФЙНї
ЅоЅЦЅЄЅЂЄЕЄѓЄЋЄщУэЄЌЄьЄЗЅяЅЄЅѓ
ПРЁЙЄЗЄЄЄоЄЧЄЫИїЄъЕБЄЏШўЄЗЄЄБеТЮ
ЄЂЄЮЅЋЅЊЅЙЄЪУцЄЧЄЙЄйЄЦЄђДЖЄИЄыЄГЄШЄЯЬЕЭ§ЄЧЄЗЄПЄЌ
ЄГЄЮЧЛЬЉДЖЕЎЩхЄЮЅЫЅхЅЂЅѓЅЙЄтЄЂЄъЄНЄЮТИКпДЖЄЮТчЄЄЕ
ЄЪЄьЄЩАћЄсЄЦЄЗЄоЄІЖЏПйЄЪЄЪЄсЄщЄЋЄЪЅЈЅЅЙ
ЄЪЄѓЄЧЄЗЄчЄІЄЋЄГЄЮЫўТДЖЁЊ
ЭЭЁЙЄЪЄНЄЮЛўТхЄНЄЮЛўТхЄЮПшЄђЖЫЄсЄЦЄЄП
ЄНЄЗЄЦКЃЄЮЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓ
ЄЕЄщЄЫЄЯ10ЧЏИхЄоЄПАуЄІЗСЄЫЄЪЄУЄЦЄЄЄыЄЋЄтЄШЄЮЕЛіЄтНаЄЦЄЊЄъЄоЄЗЄПЄЌ
ВПЄтАњЄЋЄЪЄЄВПЄтТЄЕЄЪЄЄ
ЄГЄЮЗСЄЌЄфЄЯЄъКЧЖЏЄЧЄЯЄШЁЊ
ЄЄЄфЄЄЄф
ЄЄЄФЄЮЦќЄЋБЇУшХЊЄЪОњТЄЄШЄЋВПЄЋ
РИЄоЄьЄыЄЋЄтЄЧЄЙЄЭ
ЄШЄЫЄЋЄЏЄНЄѓЄЪЅАЅщЅєЅЭЅыЄЌНщЦўВйЄЧЄЙЁЃ
ЄНЄьЄОЄьОЏЮЬЄКЄФЄЧПНЄЗЬѕЄЂЄъЄоЄЛЄѓЄЌ
ОЏЄЗЄКЄФДЖЄИЄЦЄЄЄЄПЄЄЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
КЃВѓЄДОвВ№ЄЮЅяЅЄЅѓЄЯ
ЛЭМяЮр
ЁћЅъЅмЅУЅщ2007ЧЏ
ЩђЦКЩЪМяЁЁЅъЅмЅУЅщЅИЅуЅУЅщ
ЁћЅгЅЂЅѓЅГЁІЅжЅьЅА2007ЧЏ
ЩђЦКЩЪМяЁЁЅЗЅуЅыЅЩЅЭЁЂЅНЁМЅєЅЃЅЫЅшЅѓЁЂЅдЅЮЅАЅъЁМЅИЅч
ЅъЁМЅЙЅъЅѓЅАЁЂЅЄЅПЅъЅГ
ЁћЅдЅЮЅАЅъЁМЅИЅч2006ЧЏ
ЩђЦКЩЪМяЁЁЅдЅЮЅАЅъЁМЅИЅч
ЁћЅгЅЂЅѓЅГЁІЅжЅьЅА1998ЧЏ1500ЃЭЃЬ
ЩђЦКЩЪМяЁЁЅЗЅуЅыЅЩЅЭЁЂЅНЁМЅєЅЃЅЫЅшЅѓЁЂЅдЅЮЅАЅъЁМЅИЅч
ЅъЁМЅЙЅъЅѓЅАЁЂЅЄЅПЅъЅГ
1998ЧЏЄЯЄЙЄЧЄЫМЋСГЄЪЅяЅЄЅѓТЄЄъЄиЄШАмЙдЄЙЄыУц
97ЧЏЄЂЄПЄъЄЋЄщВЙХйДЩЭ§ЄђЄфЄсЄПЄъЃгЃЯ2ЄђИКЄщЄЗЄЦЄЄЄЏУц
ЅЙЅЦЅѓЅьЅЙЅПЅѓЅЏЄђЄфЄсЄПЄъЄШЄНЄЮКЧУцЄЧЄЮЅяЅЄЅѓЄЮЄшЄІЄЧЄЙ
ЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄЯ2001ЧЏЄЋЄщЄШЄЮЄГЄШЄЧ
ЄНЄЮЄиЄѓЄЮАуЄЄГкЄЗЄпЄЪЅяЅЄЅѓЄЧЄЙЄЭ
АЪВМЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЁМЅПЭЭЄшЄъЄЮО№ЪѓЄЧЄЙЁЃ
ЂЃЅъЅмЅУЅщ2007ЁѕЅгЅЂЅѓЅГ ЅжЅьЅА2007ЁЇЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄЧЬѓШОЧЏДжШщЄДЄШЄЮШАЙк&НщДќУЪГЌЄЮНЯРЎЁЃАЕКёИхКЦЄгЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄиЄШЬсЄЗШОЧЏФЩНЯЁЂЄНЄЮИхТчУЎЄЧ6ЧЏ(!)НЯРЎЄЮИхЅмЅШЅъЅѓЅАЁЃЅшЅЙЅГЄЮЅяЅЄЅѓЄщЄЗЄЄЅЗЅъЅЂЅЙЄЕЄЮУцЄЫЄтЬРЄыЄЕЄђШїЄЈЄПЅєЅЃЅѓЅЦЁМЅИЁЃ
ЂЃЅдЅЮ ЅАЅъЁМЅИЅч2006ЁЇИЗСЊЄЗЄПЅдЅЮ ЅАЅъЁМЅИЅчЄЧТЄЄыЅъЅМЅыЅєЅЁХЊЅяЅЄЅѓЁЃОњТЄЪ§ЫЁЄЯЅъЅмЅУЅщЁѕЅжЅьЅАЄШАьНяЁЃ
ЂЃЅгЅЂЅѓЅГ ЅжЅьЅА1998ЁЪЅоЅАЅЪЅрЅмЅШЅыЁЫЁЇИФПЭХЊЄЪЯУЄЫЄЪЄъЄоЄЙЄЌЁФЄГЄЮЅяЅЄЅѓТчЙЅЄ(Оа)ЁЃШПТЮРЉЄШЄЋЕСЪАЄШЄЋЅэЅУЅЏЄЪЪЗАЯЕЄЩКЄІЅяЅЄЅѓЁЃ
ЁЁКђЧЏЄЮЅєЅЃЅЪЅЄЅЊЅУЅЦЅЃЅоЁМЅЪЄтФЙНїЅоЅЦЅЄЅЂЄЌЕоЄЄчЛВВУЄЗЄЦЄЏЄьЄыЄГЄШЄЫЄЪЄъЁЂЄНЄЮКнЄЊШфЯЊЬмХЊЄЫЄДОвВ№ЄЕЄЛЄЦЄЄЄПЄРЄЄЄЦЄЊЄъЄоЄЗЄПЁЂЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮЅяЅЄЅѓЄЌЄшЄІЄфЄЏЦЯЄЄоЄЗЄП!!!ШрЄщЄЮЪтЄпЄНЄЮЄтЄЮЄЌЁЂЅЄЅПЅъЅЂЄЫЄЊЄБЄыЅЏЅЊЅъЅЦЅЃЧђЅяЅЄЅѓЄЮЪбСЋЄђЪЊИьЄУЄЦЄЄЄыЄШИРЄУЄЦЄтВсИРЄЧЄЪЄЄЕЄЄЌЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅЊЅъЅЦЅЃЅяЅЄЅѓЁФАеЬЃХЊЄЫЄЯЩЪМСЄЮЙтЄЄЅяЅЄЅѓЄШЄЄЄІЄГЄШЄЫЄЪЄыЄШЛзЄІЄЮЄЧЄЙЄЌЁЂЄНЄЮЛўТхЛўТхЄЧКЧЮЩЄШЄЕЄьЄЦЄЄЄПОњТЄЪ§ЫЁЄђКЮЭбЄЗЁЂЄНЄЮЗыВЬЁЪХіЛўЄЮЁЫЅЌЅЄЅЩЅжЅУЅЏЄЪЄЩЄЋЄщЙтЄЄЩОВСЄђМѕЄБЄЦЄЄПЅяЅЄЅѓЄђЛиЄЙЁФЄШЄЄЄІЄЮЄЌАьШЬХЊЄЪЧЇМБЄЫЄЪЄыЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃРяИхАЪЙпЁЂЅяЅЄЅѓОњТЄЄЮИНОьЄЫЄЂЄъЄШЄЂЄщЄцЄыЅЦЅЏЅЮЅэЅИЁМЄЌЛ§ЄСЙўЄоЄьЄыЄшЄІЄЫЄЪЄъЁЂПЇФДХЊЄЫЄтЙсЄъХЊЄЫЄтЅЏЅъЁМЅѓЄЧЛРВНХЊЅЫЅхЅЂЅѓЅЙЄЮЄЪЄЄЁЂЁШЄцЄщЄЎЁЩЄЮЄЪЄЄАТФъЄЗЄПРНЩЪЄГЄНЄЌЮЩЄЄЅяЅЄЅѓЄРЄШЫЭЄПЄСЄЌЁШПЎЄИЙўЄоЄЕЄьЄЦЄЄЄПЁЩЛўТхЄЯГЮМТЄЫЄЂЄУЄПЄЮЄРЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃЅАЅщЅєЅЭЅыЄЮHPЄЫЄтЄГЄѓЄЪЄГЄШЄЌНёЄЄЄЦЄЂЄъЄоЄЙЁЂ
ЁжЄНЄЮХіЛўЄЫЁШКЧПЗЕЛНбЁЩЄШИЦЄаЄьЄЦЄЄЄПЄтЄЮЄЯАьФЬЄъЛюЄЗЄЦЄЄПЁЃЛфМЋПШМуЄЋЄУЄПЄЗЁЂЄфЄыЕЄЄЫЫўЄСЫўЄСЄЦЄЄЄПЁЃЄГЄЮЄЂЄПЄъЄЋЄщЩуЄШЄЮЁЪЅяЅЄЅѓТЄЄъЄЫДиЄЙЄыЁЫАеИЋЄЮЩдАьУзЄЌЛЯЄоЄУЄЦЄЄЄУЄПЄѓЄРЄБЄЩЄЭЁФЁЃЄЋЄФЄЦЄЮЛфЄЮЅтЅУЅШЁМЄЯЁЂЁШТПЄЋЄэЄІЁЂЮЩЄЋЄэЄІЁЪШўЬЃЄЗЄЋЄэЄІЁЫЁЩЁЃЄФЄоЄъЁЂЄшЄъЅъЅУЅСЄЧЄПЄЏЄЕЄѓЄЮЭзСЧЄЌЄЂЄьЄаЄЂЄыЄлЄЩШўЬЃЄЗЄЄЅяЅЄЅѓЄЧЄЂЄыЄШЙЭЄЈЄЦЄЄЄПЄЗЁЂЄНЄГЄЫУЉЄъУхЄЏЄПЄсЄЫЄЯКЃЦќЄЂЄъЄШЄЂЄщЄцЄыЅяЅЄЅЪЅъЁМЄЫТИКпЄЙЄыСДЄЦЄЮЅтЅЮЁЪРпШїЁЂЕЁГЃЁЫЄЌЩЌЭзЄЪЄЮЄРЄШИЧЄЏПЎЄИЄЦЄЄЄПЁЃКЧПЗЄЮЕЛНбЄЫЬЅЄЛЄщЄьЁЂХйЄђБлЄЗЄПАеЭпЄЧАюЄьЄЦЄЄЄПЛфЄђИЋЄЦЁЂЩуЄЯЄЄЄФЄЋЛфМЋПШЄЮЪтЄпЄђМшЄъЬсЄЙЄГЄШЄђДќТдЄЗЄЪЄЌЄщОаДщЄЧИЋМщЄУЄЦЄЏЄьЄЦЄЄЄПЄѓЄРЄэЄІЄЭЁЃМТКнЄЫЩуЄЮЛзЯЧФЬЄъЁЂЅЙЅЦЅѓЅьЅЙЅПЅѓЅЏЄЋЄщЛЯЄоЄУЄЦЅаЅъЅУЅЏЄЫЛъЄыЄоЄЧЄЮВсОъЄЪОњТЄРпШїЄђНљЁЙЄЫНшЪЌЄЗЄЦЄЄЄЏЄГЄШЄЫЄЪЄыЄЮЄРЄБЄЩЁФЁЃ5000ЧЏАЪОхЄЫХЯЄУЄЦТГЄЄЄЦЄЄПЅяЅЄЅѓОњТЄЄЮХСХ§ЮђЛЫЄЌЁЂЄПЄУЄППєННЧЏЁЪЄЮНаЭшЛіЁЂЄНЄЮДжЄЫРИЄоЄьЄПЕЛНбЯРЁЫЄЧНёЄДЙЄЈЄщЄьЄыЄГЄШЄЪЄЩЄЂЄУЄЦЄЯЄЪЄщЄЪЄЄЁЃЛфЄЮЅЛЅщЁМЄЫЄЯЁЂЄЂЄщЄцЄыЅЦЅЏЅЮЅэЅИЁМЄтЦУМьИњВЬЄтТИКпЄЗЄЪЄЄЁЃЅГЁМЅЋЅЕЅЙУЯЪ§ЄЋЄщЄфЄУЄЦЄЄПЅЂЅѓЅеЅЉЅщЄЌЅЊЅЙЅщЁМЅєЅЃЅЂЄЮТчЁІuлђnЄЫЪњЄЋЄьЄЪЄЌЄщЕйЄрОьНъЁФЁЃЛфЄЯЁЪЄГЄЮЅЛЅщЁМЄЮЁЫЅЗЅѓЅзЅыЄЕЄШЕЁЧНРЄђАІЄЗЄЦЄфЄоЄЪЄЄЁЃЁз
ЁЁЄГЄЮHPЄЋЄщЄЮШДПшЄЯЁЂЅЋЅѓЅЦЅЃЁМЅЪЁЪЅЛЅщЁМЁЫЄШЄЄЄІОЯЄЮСДЬѕЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃЄШЄЦЄтДЪЗщЄЧЄЙЄЌЁЂКЃИНКпЄЮШрЄЮЅяЅЄЅѓДбЄфЁШШўЬЃЄЗЄЕЁЩЄЫТаЄЙЄыЙЭЄЈЄЌЭОЄЙЄГЄШЄЪЄЏРЙЄъЙўЄоЄьЄЦЄЄЄыЕЄЄЌЄЗЄоЄЙЁЃ
ЁЁЅЊЁМЅПЄЪЄъЄЮВђМсЄђВУЄЈНёЄТЄЗЄоЄЙЄШЄГЄѓЄЪДЖЄИЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁФЁЃ
ЁЁАеПоХЊЄЫЁЂЄНЄЗЄЦЕЛНбЄђЖюЛШЄЗЄЦРИЄпНаЄЕЄьЄыШўЬЃЁЂВОЄЫЄНЄЮЬЃЖкЄЌЛўЮЎЄЫОшЄыЄтЄЮЄРЄУЄПЄъЁЂТчТППєЄЫЙЅЄоЄьЄыЄтЄЮЄРЄШЄЗЄЦЄтЁЂЄтЄЯЄфМЋЪЌЄЯЖНЬЃЄЌЄЪЄЄЁЃ
ЁЁШўЬЃЄЗЄЄЄшЄъЄтВПЄшЄъЄтЅяЅЄЅѓЄЯЅяЅЄЅѓЄШЄЗЄЦППРЕЁЪЅлЅѓЅтЅЮЁЂХСХ§ЄЫТЇЄУЄПЁЂППЄУХіЁЫЄЧЄЪЄБЄьЄаЄЪЄщЄЪЄЄЁЃ
ЁЁППРЕЄЪЅяЅЄЅѓЄПЄщЄЗЄсЄыЄПЄсЄЫЄЯЁЂЪьЄЪЄыТчУЯЄиЄЮАкЩнЄЮЧАЄШАЮТчЄЪЅяЅЄЅѓЄЮЮђЛЫЄЫТаЄЗЄЦЄЮЗЩАеЄђЫКЄьЄЦЄЯЄЪЄщЄЪЄЄЁЃ
ЁЁЄНЄЮАкЩнЄЮЧАЄШЗЩАеЄђЛ§ЄСЙчЄяЄЛЄЦЄЄЄПЄЮЄЪЄщЄаЁЂШЊЄЧЄЯМЋСГЄђДбЛЁЄЗЄшЄІЄШХиЄсЁЂМЋСГГІЄШЄЮФДЯТЄЮМшЄьЄПЧРЖШЄЮЄЂЄъЪ§ЄђЬЯКїЄЙЄыЄРЄэЄІЄЗЁЂЅЛЅщЁМЄЧЄтЁШТЄЄъМъЁЩЄШЄЗЄЦЄЮВцЄђЛІЄЗЁЂЄПЄРЄПЄРЅжЅЩЅІЁЂЅяЅЄЅѓЁЂШљРИЪЊЄПЄСЄЫЄШЄУЄЦЕяПДУЯЄЮЮЩЄЄДФЖЄђСЯНаЄЙЄыЄГЄШЄРЄБЄђПДЄЌЄБЁЂМЋСГЄЮЮЎЄьЄфЅъЅКЅрЄЫПШЄђАбЄЭЄыЄшЄІЄЪОњТЄЪ§ЫЁЄђКЮЭбЄЙЄыЄЯЄКЁЃ
ЁЁЄГЄЮЄшЄІЄЪЙЭЄЈЄЮЄтЄШЄЫРИЄоЄьЄПЅяЅЄЅѓЄЫЄЯЁЂЅжЅЩЅІЁЂЅЦЅэЅяЁМЅыЁЂЅєЅЃЅѓЅЦЁМЅИЄЮИФРЄЌЭОЄЙЄГЄШЄЪЄЏЩНИНЄЕЄьЄыЁЃ
ЁЁЄНЄьЄщИФРЄЯЁЂМЋСГЄЮЛ§ЄФТПЭЭРЁЂПРШыРЄЌЩННаЄЗЄПЄтЄЮЄШЄтИРЄЈЁЂЄНЄьЄГЄНЄЌЅяЅЄЅѓЄЌЛ§ЄФЄйЄЁШШўЄЗЄЕЁЩЁЪЁсШўЬЃЄЗЄЕЁЫЄЧЄЂЄыЁЃ
ЄЊЄЙЄЙЄсОІЩЪ
-

 ЅЏЅъЅЙЅСЅуЅѓЁІЅгЅЭЁМЅыЁЁЅГЁМЅШЁІЅРЅрЅыЅЗЅхЅєЅЃЁМЅыЁІЅЁІЅЌЅКЅЄЅц2020ЧЏЁЁ750ML
ЅЏЅъЅЙЅСЅуЅѓЁІЅгЅЭЁМЅыЁЁЅГЁМЅШЁІЅРЅрЅыЅЗЅхЅєЅЃЁМЅыЁІЅЁІЅЌЅКЅЄЅц2020ЧЏЁЁ750ML
ЅЏЅъЅЙЅСЅуЅѓЁІЅгЅЭЁМЅыЄшЄъИТФъЅяЅЄЅѓХўУхЄЧЄЙЁЊШљЁЙШљШЏЫЂЄШЄЪЄыЄДЫЋШўЅяЅЄЅѓЁЊЄНЄЗЄЦЅгЅЭЁМЅыЄщЄЗЄЄЧЛЬЉЄЪЄЌЄщЙтЄЄМЁИЕЄЧЅаЅщЅѓЅЙЪнЄФЅяЅЄЅѓЁЊХўУхЄЧЄЙЁЊ
5,280Бп(РЧ480Бп)
-

 ЅыЁІЅьЅЖЅѓЁІЅЈЁІЅщЅѓЅИЅхЁЁЃжЃфЃЦЅыЁІЅьЅЖЅѓЁІЅЈЁІЅщЅѓЅИЅхЁЁЅЭЅИЅхЅо2024ЧЏЁЁ750ML
ЅыЁІЅьЅЖЅѓЁІЅЈЁІЅщЅѓЅИЅхЁЁЃжЃфЃЦЅыЁІЅьЅЖЅѓЁІЅЈЁІЅщЅѓЅИЅхЁЁЅЭЅИЅхЅо2024ЧЏЁЁ750ML
АІЄЧЄыЄйЄТИКпЅыЁІЅьЅЖЅѓЁІЅЈЁІЅщЅѓЅИЅхЁЁШўЄЗЄЏСЧЫбЄЧМЂЬЃПМЄЄЅяЅЄЅѓЁЊКЃВѓЄЯЧђ1МяЮрХўУхЄЧЄЙЁЊЄНЄЗЄЦПЗМђХЊЄЪЅяЅЄЅѓЄНЄЮЧЏЄНЄЮЧЏЄЧЬЅЮЯЄЌЄЋЄяЄыЅНЅяЅеЄЪЅяЅЄЅѓЁЊЅнЁМЅКЁІЅЅуЅЮЅѓХўУхЄЧЄЙЁЊ
3,850Бп(РЧ350Бп)
-

 ЅэЁМЅщЅѓЁІЅаЁМЅѓЅяЅыЅШЁЁЅИЅЇЁІЅщЁІЅеЅЉЅъЁМ2020ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬЁЁЧђЁІШљЁЙУКЛР
ЅэЁМЅщЅѓЁІЅаЁМЅѓЅяЅыЅШЁЁЅИЅЇЁІЅщЁІЅеЅЉЅъЁМ2020ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬЁЁЧђЁІШљЁЙУКЛР
ЅЂЅыЅЖЅЙМЋСГЧЩФЉРяХЊЄЪЅЅхЅєЅЇРИЄпНаЄЙЅэЁМЅщЅѓЁІЅаЁМЅѓЅяЅыЅШЁЊЁЁКЃВѓЄЯПЭЕЄЄЮЅЈЅЧЅыЄЮКЦЦўВйЁЊЄНЄЗЄЦОхАЬЅяЅЄЅѓЄЯЅВЅєЅхЅыЅФЄЮЅЂЅыЅГЁМЅы14ЁѓМуДГЄЮЅЗЅхЅяЄЂЄъЅяЅЄЅѓЁЊ
4,997Бп(РЧ454Бп)
-

 ЅГЅѓЅзЅьЅтЅѓЁІЅЦЁМЅыЁЁЅАЅщЅѓЁІЅІЅыЅЙ2022ЧЏЁЁ750ML
ЅГЅѓЅзЅьЅтЅѓЁІЅЦЁМЅыЁЁЅАЅщЅѓЁІЅІЅыЅЙ2022ЧЏЁЁ750ML
ЅГЅѓЅзЅьЅтЅѓЁІЅЦЁМЅыЄЮХіХЙНщЄЮРжЅяЅЄЅѓЁЁЅЋЅйЅыЅЭЅеЅщЅѓЄЮЅдЅхЅЂЄЧЧЛИќЄЧТчЄЄЕЄЂЄыДнЄпЄЂЄыЅяЅЄЅѓЁЊ
4,246Бп(РЧ386Бп)
-

 ЅвЁМЅЩЅщЁМЁЁЅдЅЮЅЮЅяЁМЅыЁЁЅщЅѓЅВЅѓЅэЅЄЅЖЁМЁІЅпЅЭЅщЅы2023ЧЏЁЁ750ML
ЅвЁМЅЩЅщЁМЁЁЅдЅЮЅЮЅяЁМЅыЁЁЅщЅѓЅВЅѓЅэЅЄЅЖЁМЁІЅпЅЭЅщЅы2023ЧЏЁЁ750ML
АЮТчЄЪЄыЅЊЁМЅЙЅШЅъЁМЅяЅЄЅѓЁЁЅвЁМЅЩЅщЁМХўУхЁЊПЦЄЗЄпЄфЄЙЄЄЅяЅЄЅѓЄЧЄтЄНЄьЄРЄБЄИЄуЄЪЄЄЮЩЄЕЄЌРИЄЄыЅяЅЄЅѓЁЁРЖЁЙЄЗЄЏЅЏЅъЁМЅѓЄЧДѓЄъХКЄІСЧРВЄщЄЗЄЄЅяЅЄЅѓЗВЁЊ
3,960Бп(РЧ360Бп)
-

 ЅЙЅЦЁМЅеЅЁЅЮЁІЅьЅЫЅуЁМЅЫЁЁЅнЅѓЅЦЁІЅЧЅЃЁІЅШЅЄ2022ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬ
ЅЙЅЦЁМЅеЅЁЅЮЁІЅьЅЫЅуЁМЅЫЁЁЅнЅѓЅЦЁІЅЧЅЃЁІЅШЅЄ2022ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬ
ЅъЅАЁМЅъЅЂНЃЄЋЄщЅЙЅЦЁМЅеЅЁЅЮЁІЅьЅЫЅуЁМЅЫЁЊВўЄсЄЦЅГЅЙЅбЄЮЙтЄЕЄЕЄщЄЫАЪСАЄшЄъЄтПМЄпЄоЄЗЄПЅяЅЄЅѓЁЊ
3,677Бп(РЧ334Бп)
-

 ЅЕЅѓЅПЁІЅоЅъЁМЅЂЁЁЅэЅЖЁМЅШ2024ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬ
ЅЕЅѓЅПЁІЅоЅъЁМЅЂЁЁЅэЅЖЁМЅШ2024ЧЏЁЁ750ЃЭЃЬ
ЅтЅѓЅПЅыЅСЁМЅЮЄЫЦДЄьНЛЄпЄФЄЄНЄЮУЯЄЧМЋСГЄЪЅяЅЄЅѓТЄЄъЄђТГЄБЄыЅоЅъЁМЅЮЁѕЅыЅЄЁМЅЖЄЮЅяЅЄЅѓЁЁЅяЅЄЅѓЄЋЄщДЖЄИЄыЗнНбРЄЗЄЪЄфЄЋЄЧШўЄЗЄЄВЬМТЬЃЁЁЄНЄьЄђДЖЄИЄщЄьЄыЦУЪЬЄЪЅяЅЄЅѓЄЧЄЙЁЊЁЊЁЊ
3,960Бп(РЧ360Бп)
-

 ЅАЅщЅѓЁІЅбЁМЁІЅАЅщЅѓЁЁЅАЅщЅѓЁІЅЩЅЅЁІЅпЅЫЅхЅЄ2023ЧЏЁЁ750ML
ЅАЅщЅѓЁІЅбЁМЁІЅАЅщЅѓЁЁЅАЅщЅѓЁІЅЩЅЅЁІЅпЅЫЅхЅЄ2023ЧЏЁЁ750ML
ЅАЅщЅѓЁІЅбЁМЁІЅАЅщЅѓЁЪАьЮГАьЮГЁЫЄНЄЮСлЄЄЄЌЅяЅЄЅѓЄЫЄтЄЗЄУЄЋЄъЄШЩНИНЄЕЄьТчЛіЄЫЅдЅхЅЂЄЫТЄЄщЄьЄПЅЕЅєЅЉЅяЄЮПЗЄЗЄЄЅЪЅСЅхЅщЅыЅяЅЄЅѓХаОьЄЧЄЙЁЊЁЊЁЊ
5,723Бп(РЧ520Бп)
-

 ЅЗЅъЅыЁІЅеЅЁЅыЁЁЅыЁМЅИЅхЁІЅДЅыЅИЅхЁЁЅжЅщЅѓ2022ЧЏЁЁ750ML
ЅЗЅъЅыЁІЅеЅЁЅыЁЁЅыЁМЅИЅхЁІЅДЅыЅИЅхЁЁЅжЅщЅѓ2022ЧЏЁЁ750ML
ЅЙЅкЅЄЅѓЙёЖЖсЄЏЅщЅШЅЅЁМЅыЁІЅЩЅЅЁІЅеЅщЅѓЅЙЄшЄъРИЄпНаЄЕЄьЄыЦюЪЉЅАЅщЅѓЅєЅЁЅѓЁЊЅЗЅъЅыЁІЅеЅЁЅыХіХЙНщХаОьЁЊЅыЁМЅЗЅчЅѓЅяЅЄЅѓЄЪЄьЄЩСЁКйРШўЄЗЄЕЄЗЄЪЄфЄЋЄЪЮЯЄЫЫўЄСЄПЅяЅЄЅѓЁЊ
6,830Бп(РЧ621Бп)