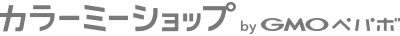„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒĄĄ„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„ÌĄÊ2018ÇŻĄËĄĄ750ML
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒĄĄ„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„ÌĄÊ2018ÇŻĄËĄĄ750ML
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„ÌĄÊ2018ÇŻĄË€Ç€čĄȘĄȘĄȘ
ąšÈÎÇä€ËșĘ€·€Æ€Î€ŽĂí°Ő
”źœĆ€Ê„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€È€Ê€ê€Ț€čĄŁ
žæ°ìżÍÍÍ1Ëܞ€ê€Ç€ȘŽê€€€€€ż€·€Ț€čĄŁ
»ä€ÎĂæ€Ç€â1Ąą2€òÁ耊ÆĂỀʄ·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€Ç€čĄŁ
°ÊÁ°€ÈÈæ€Ù€Æ€â€è€êŽőŸŻ€Êžșß€Ë€Ê€Ă€Æ€€€ë”€€Ź€€€ż€·€Ț€čĄŁ
€Ê€«€Ê€«€€€ż€À€±€Ê€Ż€Ê€ë€ÈÍŸ·Ś€ËÍ߀·€Ż€Ê€ë€Î€ŹŸï€Ç€č€Ź
Ÿ€Î„Ś„ì„č„ÆĄŒ„ž„·„ă„ó„ŃĄŒ„˄怏žźÊ€ßČÁłÊŸćŸș€ą€ëĂæ
€Ț€À€Ț€ÀÎÉżŽĆȘ€ÊČÁłÊ
€â€Á€í€ó°Â€Ż€Ï€Ê€€€â€Î€Ç€č€Ź
ÆâÍÆ€òčÍ€š€ì€ĐÎÉżŽĆȘ€ÊČÁłÊ€È€â»Ś€š€ë„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç€ą€ë€È»Ś€€€Ț€čĄŁ
ĆöĆč€Î€ȘÉŐ€č瀀€â
05ÇŻ€«03€«€œ€Î€Ű€ó€«€é€Î€ȘŒè°·€€
€ż€Ț€ËÀÚ€ì€Æ€·€Ț€Ă€ż€ê€Ț€ż·Ò€Ź€Ă€ż€ê€È€ą€ê€Ț€č€Ź
ÍÍĄč»äžÄżÍĆȘ€Ë€â€€€í€€€í€ą€Ă€ż€ł€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
€œ€ì€À€±€Ë€Ê€ó€«ÂŸ€È°ă€Š»Ś€€Æț€ì€â€ą€ë„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
șŁžć€â¶ËĄčșÙ€Ż€È€â·Ò€Ź€Ă€Æ€€€ż€€„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç€ą€ê€Ț€čĄŁ
€È€€€Š€ł€È€Ç
ż·„ô„Ł„ó„ÆĄŒ„ž2018ÇŻ€â€Î
žș߀·€Æ€€€ë€«€É€Š€«Äꀫ€Ç€Ï€Ê€€€Û€É€ËŸŻ€Ê€€ËÜżô€Ê€Î€Ç
»ÄÇ°€Ê€Ź€é°û€à€ł€È€Ïłđ€ï€Ê€€€Î€Ç€č€Ź
€ł€Î„ż„€„߄󄰀ǀŽŸÒČđ€À€±€”€»€Æ€€€ż€À€€Ț€čĄŁ
°ÊČŒ2016ÇŻ€ŽŸÒČđÊž
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„ÌĄÊ2016ÇŻĄË€Ç€čĄȘĄȘĄȘ
ąšÈÎÇä€ËșĘ€·€Æ€Î€ŽĂí°Ő
”źœĆ€Ê„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
žæ°ìżÍÍÍ1Ëܞ€ê€Ç€ȘŽê€€€€€ż€·€Ț€čĄŁ
șǶá€Ï„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€ÎČÁłÊ€â€ą€ëÄűĆÙÍî€ÁĂ怀ą€ë€è€Š€Ë»Ś€š€Ț€č€Ź
„Ö„ë„ŽĄŒ„Ë„ćƱÍÍ€Ë
°ì»țŽüŸćŸș·čžț€Ë€ą€ê€Ț€·€żĄŁ
€œ€ÎĂæ€Ç€â
€ł€łżôÇŻ€Ç€â€Û€È€ó€ÉŸćŸș€·€Æ€€€ëŽ¶€ž€Î€·€Ê€€Â€€êŒê
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€À€È»Ś€€€Ț€čĄŁ
„ï„€„ó€ÏŒûÍŚ€È¶Ą”ë€Î„Đ„é„ó„č€Ç
ČÁłÊ€ŹžČĂű€ËÊŃ€ï€ë°û€ßÊȘ€À€È€Ï»Ś€€€Ț€č€Ź
ČÁłÊ€Ź°ÂÄꀷ€Æ€€€ë€«€é€È€€€Ă€Æ
ŒûÍŚ€ŹÌ”€€€ï€±€ž€ă€Ê€Ż
”Հ˰ÊÁ°€ÈÈæ€ÙłÎŒÂ€ËÉÊÇöŽ¶€â€ą€ë„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
€Ç€â€Ê€ŒČÁłÊ€Ï€ą€ëÄűĆÙ°ÂÄꀷ€Æ€€€ë€«
€œ€Î€Ű€ó€Ï€€êŒê€ÎÎÉżŽ€œ€·€ÆÎźÄÌ€ÎłÎ€«€”
łÎ€«€”€È€€€Š€Î€Ï
€œ€ÎÌ„ÎÏ€ò€·€Ă€«€ê€ÈÇÄ°ź€·€Æ€·€«€ë€Ù€€È€ł€í€Ű€ÈÎźÄÌ€”€»€ë€œ€·€Æ
€œ€ÎÌ„ÎÏ€òÂ瀀Ż€âŸź€”€Ż€â€Ê€ŻłÎ€«€ËĆÁ€š€ë
Àž»șŒÔ€Î€Û€Š€È€·€Æ€â
€ł€ì€À€±€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€È€Ê€ì€ĐÍÍĄč€Ê€È€ł€í€«€é€Î€ŽÍŚËŸ€Ï€ą€ë€È
»Ś€€€Ț€čĄŁ
€â€Á€í€óč €Æ€âÎÉ€€€«€éÍ߀·€€€È€ÎÀŒ€ŹĄŠĄŠĄŠ
€ż€À€œ€Î€Ű€ó€ËŒê€òœĐ€·Âł€±€ì€Đ
»ÔŸìČÁłÊ€ÏŸć€Ź€ê
ÀäÂĐĆȘ€ÊČÁłÊ€ŹŸć€Ź€Ă€Æ€·€Ț€š€Đ€œ€ÎÌ„Îππ€Ă€Æ€€€Æ€â
Œê€ŹœĐ€»€Ê€Ż€Ê€êÍŸ€ê€À€·
¶Ë°ìÉô€Ç€·€«°û€á€Ê€€€â€Î€È€Ê€ë€È
Ä耀Ì܀Ǟ«€ÆÎÉ€€Êęžț€Ç€Ï€Ê€€€ÈĄŠĄŠĄŠĄŠčÍ€š€Ț€čĄŁ
„Ö„ë„ŽĄŒ„Ë„ć„ï„€„ó€Ç€Ï€â€ŠÌá€ì€Ê€Ż€Ê€Ă€Æ€€€ë„ï„€„ó€âŸŻ€Ê€Ż€Ê€€€Î€Ç€Ï€È
€œ€ó€ÊĂæ
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
ÍÍĄč€Ê·Ò€Ź€ê€Î€ą€ëĂæ€Ç€Ț€Ă€È€Š€ËÎźÄÌ€œ€·€Æ°Š€”€ì€ë„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç€Ï€È»Ś€€€Ț€čĄŁ
€œ€ó€Ê„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€è€ê
„š„Ż„č„È„éĄŠ„Ö„ê„ć„Ă„È
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„ÌĄÊ2016ÇŻĄË€Ç€čĄŁ
Àè€Ë„ê„êĄŒ„č€È€Ê€Ă€ż2015ÇŻ
€œ€Î»ț€ÎÀž»șŒÔŸđÊ󀫀é€â2015ÇŻ€œ€·€Æ2016ÇŻ€Ï
ÎÉ€€ÇŻ€È€Ê€Ă€ż€È€Î€łŸđÊó€â€ą€ê
€â€Á€í€óŽüÂÔ€Ê€Î€Ç€č€Ź
€€€Ż€Ä€«€Î„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì°û€ó€Ç€Ï€Ș€ê€Ț€č€Ź
ÂżŸŻ€Î¶Ż€€Œć€€€Ï€ą€ë€Î€«€â€·€ì€Ț€»€ó€Ź
€œ€ì°ÊŸć€Ë€œ€ÎÇŻ€œ€ÎÇŻ€ÎÀžÌżÎπζŻ€”
ÂżŸŻ€ÎŒÁ€ÏÊŃ€ï€ë€È€Ï»Ś€€€Ț€č€Ź
șÇœȘĆȘ€Ë„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„̀Ȁ·€Æ€ÎÌ„ÎÏ€ÏÈś€ï€ë€â€Î
€œ€ó€Ê”€€Ź€€€ż€·€Ț€čĄŁ
Ž°ÁŽ€Ê€ëÄêĆÀŽŃÂŹ€Æ€€Ê°û€ßÊę€òËè„Ó„ó„ÆĄŒ„ž€Ç€€ì€Đ
€œ€ì€ÏșÙ€«€Ê€È€ł€í°ă€€€òŽ¶€ž€é€ì€ë€È»Ś€€€Ț€č€Ź
À”ÄŸ€œ€ł€Ț€Ç€Î¶Ą”ëÎÌ€ą€ë€ï€±€Ç€â€Ê€Ż
€Ç€âŽńÀŚĆȘ€ÊœĐČń€€€Ç€œ€ì€Ï€œ€ì€Ç°ìŽü°ìČńĆȘ€Ê
€œ€·€Æ€œ€Î»ț€ŹÁÇÀȀ逷€€€ï€±€Ç
€ä€Ï€êÂçÀڀʞș߀ǀ襣
2016ÇŻ€â€ÎÆțČÙ€·€ż€Đ€«€ê€Ç€č€Î€Ç
€ž€Ă€Ż€ê€È°é€Æ€Æ°Š€·€Æ€€€ż€À€±€ë€Ș”ÒÍ̀΀â€È€Ű€È
€œ€ÎÀè€Ç
ÁÇÀȀ逷€€ÊȘžì€ŹÀž€Ț€ì€Ț€č€ł€È”§€ê€Ä€Ä
€ŽŸÒČđ€Ç€čĄŁ
°ÊČŒ2015ÇŻ€ŽŸÒČđÊž
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì2015ÇŻ€Ç€čĄȘĄȘĄȘ
žÀ€ï€ș€ÈĂÎ€ì€ż„Ԅ΄à„Ë„š100Ąó€Ç€€é€ì€ë
¶ËŸć€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç€č€Í
șǶá°û€ó€Ç€€€Ê€€€ÊĄŠĄŠĄŠ€È
°û€ó€Ç€·€Ț€Ș€Š€«ĄŠĄŠĄŠ€È€«
łëÆŁ€Îżô€«·î€Ç€·€ż€Ź
€Ç€â€Ț€À€Ț€ÀÆț€Ă€ż€Đ€«€ê
Œă€€€Š€Á€Ë°û€ó€Ç€â€ż€Ö€ó€œ€ÎÀš€”ÀžÌżÎπζŻ€”
Î϶Ż€€čüłÊ€äÁĄșÙ€”€â€ą€ê€Ä€Ä¶ŻżÙ€Ê„ß„Í„é„뎶€Ê€É€â
€ä€Ï€êÀš€€€Ê€ÈŽ¶€ž€é€ì€ë€È€Ï»Ś€€€Ä€Ä€â
€Ç€â€ł€ÎÀè€Ț€À€Ț€À€ą€ê€œ€Š€È
»Ś€Ă€Æ€·€Ț€Š€ł€È€âÍœÁÛ€”€ì€ë€À€±€Ë
ÆĂ€ËșŁČó2015ÇŻ
Àž»șŒÔŸđÊó€Ç€â
œë€ŻĄąŽ„Á祥€€€€ÇŻĄŁ„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ćÁŽÂ΀Ȁ·€Æ€â€€€€ÇŻĄŁ2015ÇŻ€È2016ÇŻ€ÏÁÇÀȀ逷€€ÇŻĄŁ
(Àž»șŒÔ€è€ê)ČƀΎÖĂæĄąÆü€ŹÎÉ€ŻŸÈ€êŽ„Á瀷€Æ€€€ż€Ș€«€Č€ÇĄąÉÂłČ€ÏŸŻ€Ê€«€Ă€żĄŁ€ŹĄą€â€Ă€È€âŽ„Á瀷€Æ€€€żÇŻ€Ç€â€ą€ëĄŁŒęłÏ€ÎșÇžć€Îœ”€Ë±«€Źč߀ÀżĄŁ„Ö„É„Š€ÎÎł€ÏŸźÎł€ÇĄąÎÉ€ŻœÏ€·Ąą„ą„ë„łĄŒ„ëĆÙżô€ÏÈæłÓĆȘč ĄŁ„Ü„Ç„ŁĄŒ€ÎË€«€”€Ź€ł€ÎÇŻ€ÎÆĂħĄŁ€€€Ż€Ä€«€ÎÁÇÀȀ逷€€„ô„Ł„ó„ÆĄŒ„žĄŠ„·„ă„ó„ŃĄŒ„˄怏€€é€ì€ëÇŻ€È€Ê€ë€À€í€ŠĄŁ
€È€Î€ł€È€Ç
€ł€ó€Ê„ł„á„ó„Èž«€ż€é
€ä€Ï€êżČ€«€»€Æ€Ș€€ż€€€È»Ś€Ă€Æ€·€Ț€€€Ț€č€Í
€È€€€Š€ł€È€Ç
șŁČó€Ï„Æ„€„č„Æ„Ł„ó„°Ì”€·€Ç€Î€Ž°ÆÆâ€È€”€»€Æ€€€ż€À€€Ț€čĄŁ
ËÜĆöÁÇÀȀ逷€€„ï„€„ó€Ë€Ê€ì€Đ€Ê€ë€Û€É
żÍŽÖ€ÎŒśÌż€Ă€Æ€±€Ă€ł€ŠĂ»€€€ÈŽ¶€ž€ë
€œ€ó€Ê€·€À€€€Ç€ą€ê€Ț€·€żĄŁ
°ÊČŒ2014ÇŻ€ŽŸÒČđÊž
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì2014ÇŻ€Ç€čĄȘ
„ž„ă„Ă„ŻĄŠ„»„í„č€ò»Ő€È¶Ä€ź
„Ԅ΄à„Ë„š€È€€€ŠÉÊŒï€ÎČÄÇœÀ€òżź€žÂł€±€Æ
€ł€ÎΩ€Á°ÌĂÖ€Ț€ÇŸć€ê”̀ဿ
žÉčâ€Îžșß„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€Ç€čĄŁ
·è€·€Æ·Ă€Ț€ì€żÈȘ€Ê€ÉŽÄ¶€Ç€â€Ê€Ż
€œ€ÎĂæ€Ç„Ԅ΄à„Ë„š€À€±€Ë€ł€À€ï€ê
Ëဟć€Č€ż„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
€œ€ì€Ź„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç€ą€ê€Ț€čĄŁ
ÄÌŸï„Ș„ó„ê„č„È€”€ì€ë€ł€È€âÌ”€Ż€Ê€Ă€ż€Î€ÏĆö€ż€êÁ°€Îžœș߀ǀą€ê
žÂÄê„ï„€„ó€È€·€Æ€â
€œ€Š€œ€Š€ȘÊŹ€±€€€ż€À€±€ëÂćÊȘ€Ç€â€Ê€Ż€Ê€Ă€Æ€·€Ț€Ă€ż
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
€œ€ì€Ç€â€ł€Š€ä€Ă€ÆżôÇŻ€Ë°ìČó€Ç€â
ŸŻÎÌ€ȘÊŹ€±€€€ż€À€±€ëŽî€Ó€òłú€ß€·€á€Ä€Ä€ŽŸÒČđ€Ç€čĄŁ
ĆöĆ耳€łżôÇŻ
€Û€È€ó€É€Ź€€€ï€æ€ëRMĄÊ„ì„ł„ë„ż„óĄŠ„Ț„Ë„Ô„ć„é„óĄË€ÈžÀ€ï€ì€ë
žÄżÍ€Ê€É€ÎŸź”ŹÌÏÀž»șŒÔ€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Đ€«€ê€È
€Ê€Ă€Æ€·€Ț€€€Ț€·€żĄŁ
€ż€Ț€ËÏĂÂê€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ê€É€â
€ȘŒè°·€€€·€ż€ê°û€ó€Ç€ß€ż€ê€·€Ț€č€Ź
€ä€Ï€êżŽ€Ë¶Á€Ż€Î€Ï
€œ€ì€Ÿ€ì€ÎÀž»șŒÔ€ŹĆÚĂπǀą€Ă€ż€êÉÊŒï€Ç€ą€Ă€ż€ê
Ÿú€ÊęËĄ€ä„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Î„č„ż„€„ë€Ê€É
Čż€«€·€é€ł€À€ï€ê
żź€žÈŽ€€€Æ€ż€É€êĂ怀€ż€œ€ó€ÊžÄÀ€Î€ą€ë„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
€œ€Î°ì€Ä„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€Ç€ą€ê€Ț€čĄŁ
„Ԅ΄à„Ë„š€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
„é„·ĄŒ„Ì€”€ó€ȘŒè°·€€€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç
€ł€Î„Ԅ΄à„Ë„š€Ë€ł€À€ï€Ă€żÀž»șŒÔ€â€Ș€ê€Ț€čĄŁ
„ž„ç„ŒĄŠ„ß„·„§„ë€ä„é„š„ë„ÈĄŠ„Ő„ìĄŒ„ë€â„à„Ë„š€Î€ß€Î„„ć„ô„§€Ź€ą€Ă€ż€ê
șŁ€Ț€Ç€âÊ耫€ì€ż€Î€Ï
·è€·€Æ„Ԅ΄à„Ë„š€ÏÊäœőĆȘ€Êžș߀ÎÉÊŒï€Ê€É€Ç€Ï€Ê€Ż
„á„€„ó€Ë€Ê€ë€ł€È€Î€Ç€€ë
„Ę„Æ„ó„·„ă„ë€ò»ę€ÄÉÊŒï€Ç€ą€ë€È€€€Š€ł€È€Ç€čĄŁ
„Ô„Î„Î„ïĄŒ„륹„·„ă„ë„É„Í€Ź„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€ÎÈȘ€Ç€â脄턱ĄŒ„·„ç„ó€Ë€ą€ë€ł€È€Ź
Âż€«€Ă€ż€ê
€œ€ÎĂŒ€Ă€ł€Î€Û€Š€Ç„Ԅ΄à„Ë„š€Ź€ą€Ă€ż€Î€«ĄŠĄŠĄŠ
€œ€Î€Ű€ó€Ï€ï€«€ê€Ț€»€ó€Ź
€·€Ă€«€ê€Èżź€ž€Æ„Ԅ΄à„Ë„š€ÎÀŒ€òÊ耀€Æ°é€ÆŸć€Č€ë€ł€È€Ç
€ł€ì€À€±€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€È€Ê€ë€è€Š€Ç€čĄŁ
ĄŠĄŠĄŠĄŠ€È€€€Š€ł€È€Ç
șŁČó°û€ß€ż€€ĄŠĄŠĄŠ€Ç€â°û€á€Ê€€
șŁČó€Ï°û€á€Ț€»€óĄŁ
ÆțČÙżôÎÌ€âžÂ€é€ì
żœ€·Ìő€ą€ê€Ț€»€óĄŁ
°ÊÁ°°û€ó€À°őŸĘ€Ê€É”șÜ€Ž€¶€€€Ț€č€Î€Ç
€Ž»ČčÍ€Ż€À€”€€ĄŁ
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
°ÎÂç€Ê„ï„€„ó€Ï€€€Ä°û€ó€Ç€â€œ€Î°ÎÂ瀔€òĆÁ€š€Æ€Ż€ì€ë€È€ÏžÀ€€€Ț€č€Ź
€Ç€â€ä€Ï€êÂÔ€Á€ż€€„ï„€„ó
€œ€Î€Ő€Ă€Ż€éŽ¶€È€á€É€Ê€ŻÍŻ€Ÿć€Ź€ëËąĄą»ĘÌŁ
€œ€ì€é€Ź€è€êŸćŒÁŽ¶€â€Ă€ÆłÚ€·€á€ë„ż„€„ß„ó„°Ąą€ł€í€ą€€€È€€€Š€â€Î€Ź€ą€ëÄűĆÙ
€ą€ë€È»Ś€€€Ț€čĄŁ
°ÊÁ°€Ï2014ÇŻ€Ë°û€ó€À2006ÇŻÊȘ
șŁČó2014ÇŻ€â€Î€Ç€č€Î€Ç
2022ÇŻ°Êč߀ǀ·€ç€Š€«ĄŠĄŠĄŠ
°ÊČŒ2009ÇŻ€ŽŸÒČđÊž
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì2009ÇŻ€Ç€čĄŁ
ĆöĆč€É€Š€·€Æ€â€ł€Š€€€Ă€ż„ì„ą„ą„€„Æ„à€È€Ê€ë€È
¶œÊł€·€ż”€»ę€Á€ò€Ö€Ä€±€ëÍ̀ʀä€äÀú€Ă€Æ€·€Ț€ŠÉœžœ
șŁ€Ț€ÇÂż€«€Ă€ż€è€Š€Ë»Ś€š€Ț€čĄŁ
șŁČ󀜀ζœÊł€ËĂÍ€č€ë„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
€œ€·€Æ€Ê€ó€ÈÊŁżô„ô„Ł„ó„ÆĄŒ„ž€Î„Ș„Ő„ĄĄŒ€€€ż€À€€Ț€·€żĄŁ
€Ž°ÆÆ €ż€À€€€ż€È€€Ï
ŒêÊü€·€ÇŽî€Ö€è€Š€Ê»Ò¶Ą€Ź€Ș€â€Á€ăÍ€±€é€ì€ż€è€Š€Ê€œ€ó€Ê”€»ę€Á€Ç€ą€ê€Ț€·€ż€Ź
ÆțČÙ€«€é»ț€Ź€ż€Á
șŁČ󀳀Š€€€Ă€żÊŁżô„ô„Ł„ó„ÆĄŒ„ž€Î€Ž°ÆÆ €ż€À€±€ëĄÉ°ŐÌŁĄÉ
Čż€«€ą€ë€Î€Ç€Ï€È»Ś€€€Ț€·€żĄŁ
€œ€ó€Ê€È€€Ë„€„ó„ĘĄŒ„żĄŒ„é„·ĄŒ„ÌÍ̀ζœÌŁżŒ€€Čá”î€Î„é„·ĄŒ„ÌÊŰ€êâ43€Ë€Ș€€€Æ
€ł€ó€Ê”œÒ€òÈŻž«€·€Ț€·€żĄŁ
ĄÖÆüËÜ€Ç€ÏĄą„ž„§„íĄŒ„à€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€ÏÆțČÙ€č€ëÀäÂĐÎÌ€ŹŸŻ€Ê€€€Î€ÇĄą„ì„ą„„ą„€„Æ„à€È€·€Æ°·€ï€ì€Æ€€€Ț€čĄŁ€œ€Î€ż€áĄąËÜĆö€ËłÚ€·€ó€Ç°û€à€È€€€Š€è€êĄą€Ț€ș°û€ó€Ç€ß€ż€€€È€€€Šč„ŽńżŽ€ÎÂĐŸĘ€Ë€Ê€Ă€Æ€·€Ț€€ĄąËÜÍè€ÎÌŁ€ï€€€ŹÀ”€·€ŻÍęČò€”€ì€Æ€€€Ê€€€È»Ś€ï€ì€Ț€čĄŁ»ä€ż€Á€ÏșŁ€Ț€ÇÌŁ€ï€€Âł€±€Æ€€ż·ëÏÀ€È€·€ÆĄą„Ç„Ž„ë„ž„ć„Ț„󀫀é2ÇŻ¶á€Ż€ż€Ă€ż€È€Ąą€ą€Ê€ż€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ë€ÏÄŽÏ€ȀȚ€È€Ț€ê€ŹÀž€Ț€ìĄą°Û€Ê€Ă€ż„č„ÆĄŒ„ž€ËĂŁ€č€ë€È»Ś€Ă€Æ€€€Ț€čĄŁ€œ€ł€ÇĄą€œ€Î€è€Š€ÊÌŁ€ï€€€ËĆțĂŁ€·€ż»Ń€òĂÎ€Ă€Æ€â€é€€€ż€€€Î€ÇĄą„ê„êĄŒ„č€ò°ìÇŻĂÙ€Ż€·€ż€€€ÈčÍ€š€Æ€€€Ț€čĄŁ€ą€Ê€ż€ÏĄą€É€Š»Ś€ï€ì€Ț€č€«Ą©ĄŚ
ĄĄ€ł€ÎčÍ€šÊę€Ë„ž„§„íĄŒ„à€âÂ绿Àź€Ç€čĄŁĄÖșŁĆÙĄą„ß„·„§„륊„Ù„ż„ó„Ì€òŒ«Âđ€ËŸ·€€€ÆĄą»ä€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€ÏĄą„Ç„Ž„ë„ž„ć„Ț„óžćĄą»țŽÖ€Ź€ż€Ă€ÆÌŁ€ï€€€ŹŽ°Àź€č€ë€ł€È€òłÎǧ€·€Æ€â€é€ŠČń€ò€č€ë€ł€È€Ë€·€żĄŁ·Ż€ż€Á€âĄą€Ș€€€Ç€èĄŁĄŚ€ÈͶ€Ă€Æ€€€ż€À€€Ț€·€żĄŁ
€È€Î€ł€È
€œ€Š€Ê€ó€Ç€č€Í
șŁČ󀳀Š€ä€Ă€ÆÊŁżô„ô„Ł„ó„ÆĄŒ„ž€ä€ą€ëÄűĆÙ€ÎżôÎÌÆțČÙ€č€ë€ł€È€Ç
čÍ€š€ë€ł€È€Ç€€ż€Î€Ç€č€Ź
șŁ€Ț€Ç€ÏÄÁ€·€€€â€Î”źœĆ€Ê€â€Î€È€€€Š€ł€È€Ç
€œ€ì€À€±€ŹÀèčÔ€·€Æ€Î€Ž°ÆÆâ€À€Ă€ż€È»Ś€Ă€Æ€Ș€ê€Ț€čĄŁ
șŁČó„í„ŒĄŠ„Ő„Ą„Ă„ŻĄŠ„·„ß„ì08
€œ€Îžć€Ë°û€ó€À€ł€Î„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì06
08€Ï€«€Ê€êč ɟČÁ€€€ż€À€€€ż»ĆŸć€Ź€ê€È€Ê€Ă€Æ€€€ë€è€Š€Ç
€œ€ÎÊŹ„Ę„Æ„ó„·„ă„ë€Ï€č€Ž€€€·€Ț€À€Ț€ÀŒă€€ÀźœÏ€·€€Ă€Æ€€€Ê€€ĂÊłŹ€«€È»Ś€€€Ț€čĄŁ
€œ€·€Æ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì06€ÎŽ°œÏ€·€żËÜÍè€ÎÌ„ÎÏœĐ€ż„à„Ë„š€òŽ¶€ž€Æ
ÁÇÀȀ逷€€„ï„€„ó€À€«€é€ł€œ
ÄÁ€·€€€È€€€ŠÂžș߀À€±€ÇÈÎÇä€č€ë€Î€Ç€Ï€Ê€Ż€Á€ă€ó€È€œ€ÎËÜÍè€ÎÌ„ÎÏ€òłÚ€·€ó€Ç€â€é€Š€Ù€Ż
ÈÎÇä€č€ë€ł€È
€œ€ì€Ź„ï„€„óČ°€È€·€Æ€Î»ÈÌż€Ç€ą€ë€ÈșÆĆÙłÎǧ€Ç€€ż€è€Š€Ê”€€Ź€€€ż€·€Ț€čĄŁ
ČÁłÊ€ÇÇä€ëĄą”źœĆ€Êžș߀ÇÇä€ëĄą€œ€Š€€€Ă€ż€ł€È€â°û€ßŒê€Î€ȘÆÀŽ¶€äÆĂÊÌŽ¶ĄąŽ¶€ž€Æ€â€é€Š€ł€È€œ€ì€â
€ą€Ă€Æ€â€€€€€«€È»Ś€€€Ț€č€Ź
ËÜÍè€Î€œ€Î„ï„€„ó€ÎËÜĆö€ÎÌ„ÎÏ€òĆÁ€š€ë€œ€ł€òËș€ì€Æ€Ï€€€±€Ț€»€ó€Í
€È€€€Š€ł€È€Ç
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì2009ÇŻ€Ç€ą€ê€Ț€čĄŁ
șŁČóÆțČÙ€Ï
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì2006ÇŻĄą2007ÇŻĄą2008ÇŻĄą2009ÇŻ
„š„Ż„č„È„éĄŠ„Ö„ê„ć„Ă„ÈĄĄ„í„ŒĄŠ„Ő„Ą„Ă„ŻĄŠ„·„ß„ì2007ÇŻĄą2008ÇŻĄą2009ÇŻ€Ç
€ą€ê€Ț€čĄŁ
șŁČó„Æ„€„č„Æ„Ł„ó„°€Î
„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì2006ÇŻ
€œ€ÎÍͻҀǀą€ê€Ț€čĄŁ
€ł€Î„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„̀ϰÊÁ°€â°û€ó€À·Đžł€Ž€¶€€€Ț€č€Ź
Á°Čó€Ï05€Ç
żôÇŻÁ°€Ç€č€Î€Ç€Ț€À€Ț€À„Ő„ì„Ă„·„怔€äËą€ÎÎÏž””€€ą€ëĂÊłŹ€Ç€ą€ê€Ț€·€żĄŁ
€ż€À€œ€Îž””€€”€â
ŒÁ€Ź°ă€Š€È€€€Š€Î€Ç€·€ç€Š€«
Čż€«Ëą€ÎÀč€êŸć€Ź€êÊꀏÀȘ€€€Ź€ą€êÈùșـʔ€Ëą€ÇËÄ€é€ó€Ç€€€ŻÄì€Źž«€š€Ê€€€Û€É€Î
¶Č€í€·€€„Ę„Æ„ó„·„ă„ë€â€Ä„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç€ą€ê€Ț€·€żĄŁ
€œ€ÎŒĄ€Î„Ó„ó„ÆĄŒ„ž€Ë€Ê€ë2006ÇŻ
€œ€·€Æžœșß2014ÇŻ€Ç€č€Î€Ç
€·€Ă€«€ê€È°û€ß€Ž€í€ò·Ț€šÀźœÏ€·€€Ă€żĂÊłŹ€Ë€ą€ë„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„̀ǀą€ê€Ț€čĄŁ
„°„é„č€ËĂ퀰€È
Č«¶âż§€Ë€Ë€Ö€Żžś€ë±ŐÂ΀ϰÊÁ°·Đžł€·€żż§€È€À€€€Ö°őŸĘ°ă€€
€œ€ÎÀźœÏ€Ö€ê€Ź€Š€«€Ź€š€Ț€čĄŁ
œĆžü€ÊÌȘ€Źč┟€”Éș€ï€»œĆżŽ€ÏÄ〯€É€Ă€·€ê€Èčœ€š€ë»Ń€Ï
ÇśÎÏ€Ź€ą€ê€Ț€čĄŁ
čá€Đ€·€€„Ï„ËĄŒ„ÈĄŒ„č„Ȁ΀耊€Ê„Ë„ć„ą„ó„č
€œ€Î±ŐÂ΀òžęĂæ€Ű€ÈÎź€·čț€á€Đ
čá€ê€ÈƱÍÍ€ÎĂæżÈ€ą€ë°őŸĘ€œ€Î€Ț€Ț€Ë耏€ê€Ț€čĄŁ
„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€È€€€Š€«„°„é„ó„Ż„ê„ć„Ż„é„č€ÎÇò„ï„€„ó€È€Ç€âžÀ€€€Ț€·€ç€Š€«
€œ€Î„ł„Ż€ÎÂżœĆĆȘ€ÇœĆžü€Ê±ŐÂÎ
€œ€ì€Ç€€€Æ€·€Ă€«€ê€ÈÈŽ€±€Æ€€€€œ€ÎÍŸ±€€ÎÄ耔
żŽ€ŹčâÍÈ€·€Æ€€€Ż€Î€ŹŒ«ÊŹ€Ç€â€ï€«€ë
€Ê€«€Ê€«€Ê€€·Đžł€Ç€ą€ê€Ț€čĄŁ
„É„é„€„Ő„ëĄŒ„ÄŽ¶€âœĐ»Ï€áœÏŽ¶€ż€Ă€Ś€ê€Ç€âŒ«ÁłÂ΀DŽɄ鄀
»ä€â·Đžł€œ€ó€Ê€Ë€Ê€€€Î€Ç€ł€ÎÌŸÁ°€òœĐ€č€Î€ÏžìÊÀ€ą€ë€«€â€·€ì€Ț€»€ó€Ź
„Ż„ê„ć„Ă„°€ÇŽ¶€ž€ż€â€Î€Ë€â¶ŠÄÌ€č€ëČż€«€Ź€ą€ë€è€Š€Ë»Ś€š€Ț€·€żĄŁ
ŽđËÜ€Ï°ă€Š€Î€Ç€·€ç€Š€Ź
„à„Ë„š€ÎČÌÈé€Î„Ë„ć„ą„ó„č€ò€·€Ă€«€ê€ÈŽ¶€ž€Ê€Ź€é€ą€È€Ï
Ìû€·€à€Đ€«€ê€Ç€č€Í
ÁÇÀȀ逷€€€Ç€čĄŁ
€œ€·€Æ
„š„Ż„č„È„éĄŠ„Ö„ê„ć„Ă„ÈĄĄ„í„ŒĄŠ„Ő„Ą„Ă„ŻĄŠ„·„ß„ì2008ÇŻ€ÎÍÍ»Ò€Ç€čĄŁ
”źœĆ€Ê„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç€ą€ê€Ț€č€Ź
€œ€ÎĂæ€Ç€”€é€Ëżô€ÏŸŻ€Ê€€€ó€Ç€·€ç€Š€Í
„à„Ë„š€Î„í„Œ€Ç€ą€ê€Ț€čĄŁ
€Ê€ó€«ÆĂħĆȘ€Ê„š„Á„±„Ă„È€Ç€ą€ê€Ț€č€Ź
șŁČóÆțČÙ€Ź2007ÇŻĄą2008ÇŻĄą2009ÇŻ€Ç€ą€ê€Ț€čĄŁ
€œ€ÎĂæ€ÇșŁČó08
ÁáÂźÈŽÀò€Ç„°„é„č€ËĂ퀰€È
08€Ê€Ź€é°«ż§Ąą„č„€„«ż§€È€Ç€â€€€€€Ț€·€ç€Š€«
€œ€Îż§€Ê€Œ€«°őŸĘĆȘ
čá€ê€Ï
„Đ„é·Ï€ÎŽ±ÇœĆȘ€Êčá€ê€Ë„č„Ń„€„čČĂ€ï€ê
Ăź€Î„Ë„ć„ą„ó„č€âÍÏ€±čț€ß€Ț€čĄŁ
€É€ł€«„Ń„ê„Ă€È„„ê„Ă€È„š„Ă„ž€Ź€€€€Æ€€€ë°őŸĘ
€œ€Îč┟€Ê±ŐÂ΀ò°û€á€Đ
„Ż„ê„č„ż„ëĄȘ
„«„ê„Ă„«„ê€Î„É„é„€€Ç€č€Ź
Ž„€€€ż°őŸĘ€Ç€É€ł€Ț€Ç€âÂł€Ż„ß„Í„é„뎶€Î€è€Š€Ê„í„Œ
€ł€Á€é€â„à„Ë„š€ÎČÌÈé
€œ€ì€Ź€Ê€«€Ê€«¶áŽó€ê€Ź€ż€€°őŸĘ»ę€Á€Ê€Ź€é„Ä„ó€È€·€Æ€Ș€ê€Ț€č€Í
ĄÉ„č„ï„í„Ő„č„ĄŒ€Î„Đ„é€Î€è€Š€Ê„·„ă„ó„Ń„óĄÉ
€È€Ç€â€€€€€Ț€·€ç€Š€«
€Ț€À€Ț€À¶Ż€Ż„«„Ă„Á„ê€È€·€żÆ©ÌÀŽ¶€ą€ëł»€ËŒé€é€ì€Æ€€€ë
„í„Œ„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€ÈŽ¶€ž€Æ€Ș€ê€Ț€čĄŁ
€Ç€â€œ€Î°Ì€Îč—€ÏËȚżÍ€Ë€Ï·Ś€êĂ΀ì€Ê€€€Û€É€Î€â€Î€òŽ¶€ž€Ț€čĄŁ
șŁČó„饊„Ż„í„ș„êĄŒĄŠ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„Ì06°û€ó€Ç¶Ż€Ż»Ś€Š€Î€Ź
€·€Ă€«€ê€È°û€ß€Ž€í€Ë€Ê€Ă€ż€ł€Î„Ő„Ą„Ă„ŻĄŠ„·„ß„ì€ò°û€ó€Ç€ß€ż€€ĄȘ
€É€ŠœÏ€·€Æ€€€Ż€Î€«ÇÒ€ó€Ç€ß€ż€€ĄȘ
€È€€€Š€ł€È€Ç€č€Í
€È€€€Š€ł€È€Ç
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć
”źœĆ€Ê„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€Ç€ą€ë€ł€È€ÏŽÖ°ă€€€ą€ê€Ț€»€ó
€Ç€â€Á€ă€ó€Èžț€čç€Ă€Æ
€œ€ÎÌ„ÎÏ€òŽ¶€ž€Æ€€€ż€À€€ż€€ÀźÄ耔€»€ÆłÚ€·€ó€Ç€€€ż€À€€ż€€
€Œ€Ò€è€í€·€Ż€ȘŽê€€€€€ż€·€Ț€čĄŁ
°ÊČŒ„€„ó„ĘĄŒ„żĄŒÍÍŸđÊó
Jérôme Prevost
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
ĂÏ¶èĄĄ„â„󄿥Œ„Ë„ć„„ÉĄŠ„é„ó„襹„°ĄŒÂŒ
€€êŒêĄĄ„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒ
„Ő„é„ó„č€ÎËÌÀŸ8„„í€Ë°ÌĂÖ€č€ë„°ĄŒÂŒ€ÏĄą„â„󄿥Œ„˄楊„ÉĄŠ„é„ó„čĂ϶è€Ò€€€Æ€Ï„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ćĂÏÊę€ÇșÇ€âË̀˰ÌĂÖ€·€Æ€€€ëĄŁ€ł€ÎÂŒ€ÏÆó€Ä€Î”րˀπ”€Ț€ì€ÆÆÈŒ«€Î„Ż„ê„Ț€ŹÈś€ï€Ă€Æ€€€ëĄŁ„°ĄŒÂŒ€Ë€ą€ë„Ś„ì„ô„©ĄŒ€ÎÈȘ€ÏĄą”Ïż€Ë€è€ë€È900ÇŻÂć€Ë€č€Ç€Ë„Ö„É„Š€ŹșÏÇĘ€”€ì€Æ€€€ż€é€·€€ĄŁÈà€Ï€ł€ÎÈȘ€ÎÌŸ€ò„°ĄŒÂŒ¶á€Ż€Ë€ą€ëœ€Æ»±ĄĄÊ„ìĄŠ„Ù„źĄŒ„ÌÇÉĄË€ÎÌŸ€«€é€È€Ă€Æ€€€ëĄŁ„ą„ô„ŁĄŒ„ș€Ë€ą€ëŸú€łŰ軀dzۀó€À„Ś„ì„ô„©ĄŒ€ÏĄą1997ÇŻ€Ë„ž„ăĄŒ„ŻĄŠ„»„í„č€Î„ȘĄŒ„ÊĄŒ·ó„ï„€„ó„áĄŒ„«ĄŒ€Ç€ą€ë„ą„ó„»„ë„à€ÈœĐČń€€ĄąÉÊŒïĄąĆÚŸí€òÊĘŸÚ€”€ìĄą°ÊÍè„»„í„č€Î„»„éĄŒ€Ç„č„ż„Ă„Ő€È€·€ÆÆŻ€€Ê€Ź€éĄąŒ«ÊŹ€Î„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ć€ò€€Ă€Æ€€€ëĄÊ€â€È€â€ÈŒ«ÊŹ€Î„»„éĄŒ€Ï»ę€Ă€Æ€€€Ê€«€Ă€żĄËĄŁ„Ó„Ș„Ç„Ł„Ê„ß€Ç„Ô„ÎĄŠ„à„Ë„š€Î€ß€òșÏÇĘ€·ĄąŸú€»ț€Ë€Ï°ĄÎČ»À€ò»È€ï€Ê€€ĄŁ1998ÇŻ„ô„Ł„ó„ÆĄŒ„ž€ò2001ÇŻ1·î€Ëœé„ê„êĄŒ„襣
șÏÇĘ „Ó„Ș„Ç„Ł„Ê„ß
șÏÇĘÉÊŒï „Ô„Î„„à„Ë„šĄą„Ԅ΄„Î„ïĄŒ„륹„Ô„ÎĄŠ„°„êĄą„·„ă„ë„É„Í
Œ«ŒÒÈȘÌÌÀŃ 2.2ha
ĆÚŸí șœŒÁ€À€ŹĄą80„»„ó„Á„áĄŒ„È„ëČŒ€Ë€Ï€â€í€ŻÊŽĄč€Ë€Ż€ș€ì€ä€č€€łłÌ€ÎČœÀĐÁŰĄŁł€€ÎĆڀȻł€ÎĆÚ€ŹÆț€êșź€ž€êĄążô„áĄŒ„È„ë€Ș€€ËĆÚŒÁ€ŹÊŃ€ï€ëĄŁ
Ÿú€ ĂźÈŻčÚ/ĂźœÏÀź€òčÔ€Ă€Æ€€€ëĄŁż·ĂźÎš€Ï10Ąó€Ë€âËț€ż€Ê€€€ŹĄąșŁžć€ÏÁę€ä€·€Æ€€€ŻÍœÄêĄŁ
»Ä€ê€ÏŁ±ĄąŁČĄąŁłÇŻ»ÈÍŃ€ÎĂź€ò»È€Ă€Æ€€€ëĄŁŸú€»ț€Ë€Ï°ĄÎČ»À€òĆșČĂ€»€șĄŁ
„É„”ĄŒ„ž„ć€ÏčÔ€ï€Ê€€ĄŁ
„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒĄÔ€ï€ż€·€Î„ï„€„óŽŃĄŐ
Ąœ„Ö„É„ŠÈȘ€ÇĄąÆŻ€ËȘ€ŹČÖÊŽ€äÌȘ€òœž€á€ë€Ë»ś€żșî¶È€«€éĄą„«ĄŒ„ô€Ç€Î»Ć»ö€Ț€ÇĄœ
2002ÇŻœ©ĄĄ„ž„§„íĄŒ„àĄŠ„Ś„ì„ô„©ĄŒŒčÉź
„ï„€„ó€ËœđÌŸ€č€ë€Î€ÏÂçĂÏ
»ț€Îčï°ő€ÎÀŚ€òĂ”€í€ŠĄŁ
Ł¶Ł”Ł°ČŻÇŻ€âÁ°€Î€ł€ÈĄą¶ČΔ»țÂć€ÎœȘ€ï€ê€ŹĄą°ÜčÔŽü€Ë€ą€ż€ëĄŁ
ł€€Îżć€ÈĄąÂçĂÏ€Îżć€È€â€€€Š€Ù€șœ€ŹÀž€Ț€ì€żĄŁ€œ€·€Æł€żć€Ź€Ò€ĄąČœÀĐÁŰ€ÈÇŽĆÚÁŰ€Ź€ą€é€ï€ì€żĄŁÉ̀Οć€Ë€ÏĄąČĐÂÇÀĐ€ÎÇíÊÒ€ŹÂÏÀŃ€”€ì€żĄŁ€ł€ì€é€ŹĄąÁĂ€Ë€Ê€ëÊȘŒÁ€Ç€ą€ëĄŁ€œ€·€ÆżÍ€Ź»Ń€ò€ą€é€ï€·€żĄŁ
€œ€ł€ËČŁ€ż€ï€ëĄąÊĘÇźÀ€Ź€ą€Ă€ÆĄąÆđ€é€«€ÇĄą€·€Ê€ä€«€ÊÂçĂπΟć€ËĄÊżÍŒê€ò€«€±€ëÍŸĂÏ€ł€œ€ą€Ă€ż€ŹĄËÈà€é€Ï15À€”Ș€«€éĄą„Ö„É„Š€òżą€š»Ï€á€żĄŁÇŽĆÚ€ŹĂÛ€ĄąșœĂÏ€ŹÏ€é€ČĄąČĐÂÇÀЀǰŠÉ€ì€ż„ï„€„ó€Î€ż€á€ËĄŁ
€œ€ÎÂçĂÏ€Źčï°ő€ò€·€ż„ï„€„ó€Î€ż€á€ËĄŁ
ÀźœÏĆÙĄ§·ŃÂł€Î€ż€á€Î„«„ź
ĄĄČÌÈé€ÎœÏ€·¶ńčç€òłÎǧ€·€Ê€Ź€éĄąœÏ€·€ż„Ö„É„Š€òĆŠ€àĄŁČÌčŒ€ŹœÏ€·Ąą»À€Ź¶Ż€č€ź€ë·üÇ°€Ź€Ê€Ż€Ê€Ă€żșąčç€òž«·Ś€é€€€Ä€ÄĄą„ï„€„ó€ÎËÜĆö€ÎÇŰčü€È€Ï„ß„Í„é„ë€Ç€ą€ë€ÈčÍ€š€Ê€Ź€éĄŁ
ĄĄ”€°”Œ°„Ś„ì„č€òÍŃ€€ĄąÊüĂÖŒ°€Î·Ú€€„Ç„Ö„ë„ĐĄŒ„ž„ćĄÊÈŻčÚÁ°€ÎĆĂČŒ€ČĄË€ÈĄąÂàż§€·€Ê€€ÄűĆـΰìČó€À€±€Î°ĄÎČ»ÀĆșČĂĄÊ蔀š€á€ËĄą5„°„é„à/„Ű„Ż„È„ê„Ă„È„ëĄËĄŁ
ĄĄĆŠ€ßŒè€ê€ŹĄąŒçÂÎĆȘ€Ê»ČČĂ€òÍŚ€č€ëč԰ـǀą€ë€ł€È€ÏĄą€č€°€”€ȚÇŒÆÀ€Ź€€€Ż€À€í€ŠĄŁ
€ł€Î€È€„ô„Ł„Ë„ć„í„ó€ÏĄą„Ö„É„ŠČÌ€ŹœœÊŹ€Ë°é€Ă€ż€ÈÈœĂÇ€·€ż€ą€Č€ŻĄąČ̌€òÂçĂÏ€«€éÀÚ€ê΄€č·èÄê€òČŒ€č€Î€Ç€ą€ëĄŁ
ĄĄ€ż€È€šĄą„Ö„É„ŠČÌ€ŹĂÖ€«€ì€Æ€€€ëŸőÂÖ€ŹÊŃ€ï€ë€ł€È€Ë€Ê€í€Š€È€âĄą€ł€ÎœÖŽÖ€òĆę°ì€ą€ë·À”Ą€È€·€ÆĄą€č€Ê€ï€ÁĄąÀÚ€ê΄€”€ì€ż„Ö„É„ŠČÌ€ŹŽÄ¶€ò°Û€Ë€·€ż€À€±€ÇÉÔÊŃ€ÎÌż€òÊĘ€Ă€Æ€€€ë€ÈŽÇĐö€·€Ê€Ź€éĄąÀž€€Æ€€€ł€Š€Ç€Ï€Ê€€€«ĄŁ
ĄĄ
ÉÊŒïĄ§žę€ËÆț€ì€ëÁ°€ÎÌŁ
ĄĄÍŃ€€€é€ì€ëÉÊŒï€ÏÍŁ°ìĄą„Ô„ÎĄŠ„à„Ë„šĄŁ„à„€„æ„Ő„§ĄŒ„ë€Ë€è€ì€ĐĄą„à„Ë„š€È€€€ŠÌŸÁ°€ŹșÇœé€ËžÀ”Ú€”€ì€ż€Î€Ï16À€”Ș€Ë€”€«€Î€Ü€êĄą1539ÇŻ€ÎĄÖCh-„š„Æ„Ł„š„ó„̀΄քɄŠ±àĄŚ€Ë€«€«€ï€ëĄŁ
ĄĄ€œ€ÎÇò€€ŸźÇțÊŽ€òż¶€Ă€ż€è€Š€ÊÍՀ΀»€€€ÇĄąĄÖ„à„Ë„šĄŚĄÊÊŽČ°ĄË€ÈžÆ€Đ€ì€żĄŁ
ĄĄ€â€Š€Ò€È€Ä€ÎžÆ€ÓÌŸ€ÏĄÖ„â„ê„è„óĄŠ„ż„ł„ÍĄŚ€ÇĄą€ł€ì€Ï„àĄŒ„ążÍ€ÎÆüŸÆ€±€·€żÀőčő€€ż§€òÏąÁÛ€”€»€ëĄÊŁÆĄŠ„ô„Ą„Š„ż„ÄĄËĄŁ
€ą€ë€€€ÏĄąÀźœÏ€·€ż€È€€ËŒš€čĄą„Ô„ÎĄŠ„Î„ïĄŒ„ë€è€ê€âșĘΩ€Ă€żÀÄ€€ż§€ÎČÌÈé€æ€š€ËĄÖ„Ö„ëĄŒĄŠ„à„Ë„šĄŚ€ÈžÆ€Đ€ì€ż€È€«ĄÊŁÇĄŠ„·„ă„Ă„ŃĄËĄŁ
ĄĄ€Ò€È€Ï±ęĄč€Ë€·€ÆĄąČžĂ΀é€ș€Ê»ëÀț€ò€ł€ÎÉÊŒï€ËĆê€Č€«€±€ëĄŁ
„·„ă„ë„É„Í€ÎÍșÊÛ€”€ä„Ô„ÎĄŠ„Î„ïĄŒ„ë€ÎÎ϶Ż€”€òÏ€é€Č€ëĄąŽËŸŚșà€Î€è€Š€Ê„Ö„É„Š€È€·€ÆČáŸźÉŸČÁ€č€ë€Î€ÀĄŁ
€ÎÍșÊÛ€”€ä„Ô„ÎĄŠ„Î„ïĄŒ„ë€ÎÎ϶Ż€”€òÏ€é€Č€ëĄąŽËŸŚșà€Î€è€Š€Ê„Ö„É„Š€È€·€ÆČáŸźÉŸČÁ€č€ë€Î€ÀĄŁ
ĄĄ€·€«€·ĄąÆ─€”€æ€š€ËÆâÉô€ËÊÄ€ž€ł€â€Ă€ż€«€Î€è€Š€ËÌ©œž€č€ëĄą€ł€ÎŸźÎł€ÇČÌÆù€ÎÂż€€„Ö„É„ŠČÌ€òŽŃ»Ą€č€ë€ÈĄą€ł€ÎÉÊŒï€À€±€ò°é€Æ€è€Š€È€€€Š»Ś€€€ŹÍŻ€”Ż€ł€Ă€żĄŁ
Ž±ÇœĆȘÏ«ÆŻ
ĄĄÀž€€Æ€€€ëĆÚĄŁœüÁđșȚ€ÎÉÔ»ÈÍŃĄŁĂÏÉœ€Ț€Â€«€ËÄ„€ëșŹ€ËÂĐ€č€ë„È„é„Ż„żĄŒ€ÎžúČÌĄą€Ê€É€Ê€ÉĄŁ ÀžĂÏ€ò€ł€Í€ë„Ń„óżŠżÍ€Î€è€Š€ËĄąĆÚĂÏ€òĄÖ€ł€Í€ëĄŚ€ł€È€Î±Ù€ÓĄŁĆÚ€ÏĄą·Ą€êÊÖ€·€ł€œ€č€ìĄą·è€·€ÆčÌ€·€Ï€·€Ê€€ĄŁĆÚ€òĄą„ô„Ł„Ë„ć„í„ó€ŹÊ ä€č€€€è€Š€Ë€č€ë€ÈƱ»ț€ËĄą€ä€”€·€ŻĆÚĂÏ€ËÀžÌż€òŒű€±€ëĄŁ€Ä€Ț€ë€È€ł€íĄąĆÚĂÏ€ËÂĐ€č€ëŒêÆț€ì€È€ÏĄąÆùŽ¶ĆȘŽ¶À€Ë€è€ëč԰ـǀą€êĄążąÊȘ€ÎÆâ±ü€ą€ë€€€ÏÈëœêĄÊÆâÌ©€ÊÉôÊŹĄË€È€ÎÄŸŽ¶ĆȘ€ÊžòŽ¶€Ç€ą€êĄąÂçĂÏ€ÎșÆÈŻž«€Ç€ą€ëĄŁ
ĄĄ»ä€ż€Á€Î„Ö„É„ŠÈȘ€Ï€Ț€żĄąœ©€ÎœȘŽü€ËÍŐ€ŹÍî€Á€żžćĄążŒ€ŻčÌ€”€ì€ëĄŁĆ߀ΜȘ€ï€ê€«€é„ô„§„ì„Ÿ„óĄÊ„Ö„É„Š€Îż§ÉŐ€ŽüĄË€Ț€Ç€ÎŽÖ€ËĄą»°Č󀫀éžȚČó€Û€É»šÁđ€òŒè€êœü€ŻĄŁ
ĄĄ Ćڀ˻πȚ€êĆڀ˜Ș€ï€ëĄÖĂÏŸćÏ«ÆŻĄŚ€Î€«€ż€ï€é€ÇĄążąÀž„”„€„Ż„ë€ò€Ë€é€ó€ÀĄÖ¶ő”€Ăæ€Îșî¶ÈĄŚĄœĄœ·ŸÀĐĄÊ„·„ê„«ĄË€È„ÏĄŒ„Ö„Æ„ŁĄŒ€ÎÊźÌžĄœĄœ€ŹÊÂčÔ€·€Æ€č€č€á€é€ì€ëĄŁ€ł€Î»Ć»ö€ÏĄą„Ö„É„Š€È€€êŒê€ÎÁĐÊę€Ë€È€Ă€ÆĄą€€€ï€Đ¶ŃčŐ€ÎșÆČúÉüșî¶È€Ë€Ê€ë€Î€Ç€ą€ëĄŁ€ł€Îșî¶È€ÏĄąÎŸŒÔ€ÎËÜÀ€«€é°ï€ì€ë»țŽÖ€À€ŹĄąË»€·€€ÆüĂæ€òÈò€±€ÆÄ«Áု€ą€ë€€€ÏÆüÊë€ìĂÙ€Ż€ËŒÂčÔ€”€ì€ëĄŁ€ą€Č€Ż»ä€ż€Á€ÏĄąĄÖÌ©ÎČԀâ€É€€Î€€êŒêĄŚ€È€«ĄÖł°Æ»€Î„ô„Ł„Ë„ć„í„óĄŚžÆ€Đ€ï€ê€”€ì€ë»ÏËöĄŁ €œ€€€Ä€ÏĄąÂ瀀€Ë·ëčœĄȘ
ÂçĂπ˷žÎ±€”€ì€Æ
ĄĄÂæÌÚ€ÏĄąÉƀǀą€ëĄŁ»ä€ż€Á€Î„Ö„É„ŠÈȘ€Ëœé€á€ÆżąŒù€·€ż€Î€ÏĄą1962ÇŻ€Î€ł€ÈĄŁÂæÌڀτŻ„ÇĄŒ„ë€ÎĄÖ„ê„Ń„ê„ąĄá„ë„Ú„č„È„ê„č3309ĄŚ€ÇĄą€«€Ä€Æ„·„ă„ó„ŃĄŒ„Ë„ćĂÏÊę€Ç€ÏŒçÎź€Ç€ą€Ă€ż€ŹĄą€€€Ț€Ç€ÏžÜ€ß€é€ì€Ê€€ĄŁ€È€Ă€ÆÂŰ€ï€Ă€ż€Î€ÏĄą€€ï€á€ÆŒùÀȘ€Ź¶Ż€Ż€ÆÂżŒęÎÌ€ÎĄÖ41bĄŚ€ÇĄą€È€ê€ï€±„Ô„ÎĄŠ„à„Ë„š€ËÍŃ€€€é€ì€ëĄŁ
ĄĄ€·€«€·Ąąœăżè€ÇÁÇÄŸ€ÊÁÇÀȀ逷€€„ï„€„óĄÊC.„ž„ç„ȀΥք·„΄󥊄Մé„óĄŠ„ÉĄŠ„Ô„šĄŚĄąD.„À„°„΀Υք„ć„ô„§ĄŠ„ą„č„Æ„í„€„ÉĄŚĄË€òÌŁ€ï€Ă€ż·ëČÌĄą„Ő„é„óĄŠ„Ô„šĄÊÂæÌÚ€òÍŃ€€€ș€ËĄąÄŸ€«żą€š€č€ë€ä€êÊęĄË€Çżą€š€Ä€±€ë»î€ß€ŹĄą»ä€ż€Á€Î·ŸŒÁĆÚŸí€ÎĂπǀâżÊčÔĂæ€Ç€ą€ëĄŁŒ«Íł€Ê„ï„€„ó€Î€ż€áĄąÄö€òŸć€Č€è€ŠĄŁ
Œ«Áł€Ê„ï„€„óĄÊun vin de NatureĄË€Î€ż€á€Î°ĆÌÛ€ÎλČò
ĄĄŸú€€È€ÏĄąžòÎźĄŠžÆ”ÛĄŠł«ČÖĄŠŽË€ä€«€ÊÀźœÏ€È€€€ŠĄą€”€Ț€¶€Ț€ÊłèÆ°€ÈŒ«žÊÈŻĆž€ò€È€Č€ëĄą°ìÏą€Î·À”Ą€Ç€Ê€Ż€Æ€Ï€Ê€é€Ê€€ĄŁ€œ€ì€òŒÂžœ€č€ë€ż€á€Ë€ÏĄąÌÚÀœ€ÎËúĄÊ„Ż„ꄶ„êĄŒ„ÉĄË€È€âžÀ€Š€Ù€ŸźĂźĄÊÍÆÎÌ228„ê„Ă„È„ëĄË€ŹÉŹÍŚ€Ç€ą€ëĄŁÌÚ€ÈČ̌€Όè€êčç€ï€»€ÎÌŻ€ÏĄą°ĆÌÛ€ÎǧĂ΀ʀɀǀπʀŻĄąÌÀÇò€Ê»öŒÂ€Ç€ą€ëĄŁ
ĄĄÈŻčÚ€ÏÌîÀžčÚÊì€Ë€è€Ă€ÆŒ«ÁłÈŻÀžĆȘ€Ë»Ï€Ț€êĄą€œ€ÎÇŻ€ÎÀŒÁŒĄÂè€ÇĄąŽË€ä€«€Ê€€€·¶î€±Â€Ç€â€Ă€ÆżÊ€àĄŁ€œ€·€ÆĄąœŐ€ÎœȘ€ï€ê€Ț€ÇÂł€ŻË蜔€ÎĘ„Æț€ìĄÊ„Đ„È„ÊĄŒ„ž„ćĄË€ŹĄą„ê„ș„à€ò·Á€Ć€Ż€ëĄŁ
ĄĄ»ä€ż€Á€ÎĄÖł«ÊüŒ°„»„éĄŒĄŚĄÊ„·„š„륊„Š„ô„§ĄŒ„륚ĄÖÏȘĆ·Œ°ĄŚ€Î°ŐÌŁĄË€Î€Ê€«€ÇĄą€Ș€Î€ș€ÈÎ䔀€Ź„ï„€„ó€Î€Ț€ï€ê€ò°Ï€à€è€Š€Ë€·€ÆÆ°€ŻĄŁ6·î€Ë„ï„€„ó€Ï„Ó„ó”̀န€ì€ëĄŁ€œ€ÎșĘ€ÎčçžÀÍŐ€ÏĄąĄÖ€Ț€ë€Ž€ÈĄŚĄŁ€€€Ă€”€€Œê€òČĂ€š€ș€ËÀž€Î€Ț€ȚĄÊ„ąĄŠ„Ż„ê„ćĄË€òÊʀĀż€áĄąÀ¶ÀĄ€âßÉČá€â€”€ì€Ê€€ĄŁ€œ€ł€ËĄąż·€ż€Ê„š„Í„ë„źĄŒ€òĂ퀰ĄÊ„Ś„êĄŒ„șĄŠ„ÉĄŠ„àĄŒ„襚”ŻËąÍŃ€ÎĆüÊŹĄŠčÚÊì€ÎĆșČĂĄËĄŁ€ą€È€ÏĄą„«ĄŒ„ôÆâ€Ë„ӄ󀎀ÈÊüĂÖ€·€ÆĄąËș€ì”î€ë€Î€ßĄŁœÏÀź€ËĂŁ€·€ż„Ó„ó€ò°ú€Ÿć€ČĄą¶őĂæ€Ç„Ç„Ž„ë„ž„ć„Ț„óĄÊĆĂ°ú€ĄË€·€ÆĄą„·„í„Ă„Ś€ò€ï€ș€«€ËĆșČĂ€·ĄÊ°ìËÜĆö€ż€ê2.5„°„é„à€Î„Ö„É„ŠĆüĄËĄą€Ê€ë€ż€±Œ«Áł€ÎŸőÂÖ€ò»Öžț€·€Ä€Ć€±€ëĄŁ
€È€â€ËÊâ€à
ĄĄÀœËĄ€ÎÈëÌ©€òŒé€ë€ł€È€ŹÀźžù€ÎÍŚ°ű€Ç€ą€ëĄą€È€ß€Ê€”€ì€Æ€€€ë€ł€Î¶ÈłŠ€ÇĄąÆóżÍ€Î„ô„Ł„Ë„ć„í„󀏶šÎÏ€č€ë€ł€È€ÏĄą€€ï€á€Æ°ÛÎă€Ê€ł€È€Ë°€č€ëĄŁ3ÇŻÁ°€«€é„ą„ó„»„ë„àĄŠ„»„í„č€ÏĄążŽ€ÈÀșżÀ€òł«€€€Æ»ä€ż€Á€òÆł€Ąą»ä€ż€Á€ÎŒ«ÈŻĆȘ€ÊžœŸìžŠœ€€òž«Œé€Ă€Æ€Ż€ì€żĄŁÈà€ÎĄÖ»ĆÁđ€ÎÊžČœĄŚ€ÏĄąÏĂ€ËŒȘ€ò·č€±ĄąÇŠÂŃ€·ĄąŽőËŸ€ò»ę€Ä€ł€È€Ç€ą€Ă€ÆĄąÈà€«€éłŰ€ó€À€ł€È€ÏĄąșÇœȘĆȘ€Ë€ÏŒĄ€ÎžÀÍՀ˿Ԁ€ëĄŁ
€â€Ă€È€â„·„ó„Ś„ë€Êč԰ـ΀ʀ«€Ë
Ÿï€Ë„æ„ËĄŒ„Ż€Ê€â€Î€Ź€ą€ë
€Ș€č€č€áŸŠÉÊ
-

 „Ż„ê„č„Á„ă„óĄŠ„Á„ÀĄĄ„ą„š„€„Ș„Š2023ÇŻĄĄ750ML
„Ż„ê„č„Á„ă„óĄŠ„Á„ÀĄĄ„ą„š„€„Ș„Š2023ÇŻĄĄ750ML
„é„·ĄŒ„Ì„»„ì„Ż„·„ç„ó€è€êĂíÌ܀΄Ż„ê„č„Á„ă„óĄŠ„Á„ÀĄȘ€ł€ł€Ë€·€«€Ê€€€Ê€ó€È€â€€€š€Ê€€À€łŠŽŃżŒ€ßœžĂæÎÏŒ«Íł€òŽ¶€ž€ë„ï„€„óĆțĂć€Ç€čĄȘ
15,085±ß(ÀÇ1,371±ß)
-

 „ą„é„óĄŠ„ë„Ê„ó„ÀĄá„Ő„Ą„Ă„·„楥„Ó„ć„ŒĄŠ„»„ë„É„óĄĄ„á„ÈĄŒ„ÉĄŠ„ą„ó„»„č„È„é„륥„í„ŒĄŠ€Ú„Æ„Ł„ą„óNVĄĄ750ŁÍŁÌ
„ą„é„óĄŠ„ë„Ê„ó„ÀĄá„Ő„Ą„Ă„·„楥„Ó„ć„ŒĄŠ„»„ë„É„óĄĄ„á„ÈĄŒ„ÉĄŠ„ą„ó„»„č„È„é„륥„í„ŒĄŠ€Ú„Æ„Ł„ą„óNVĄĄ750ŁÍŁÌ
2024ÇŻ„Ó„ó„ÆĄŒ„žż·ÊȘÆțČÙĄȘœŐĄÁœéČÆ€ÎÉśÊȘ»íĆȘ€Ú„Æ„Ł„ą„óĄȘŸŻ€·ÂçżÍ€Ă€Ę€ŻÀڀʀŻŽĆ€ä€«€ÇœÀ€é€«€€„Ó„ć„ŒĄŠ„»„ë„É„óĄȘ
3,677±ß(ÀÇ334±ß)
-

 „Ő„é„ó„œ„ïĄŠ„”„óĄŠ„íĄĄD'arnouvaé s'i plleut, mett'ous yens 2023ÇŻĄĄ750ŁÍŁÌĄÊ„·ĄŒ„É„ëĄË
„Ő„é„ó„œ„ïĄŠ„”„óĄŠ„íĄĄD'arnouvaé s'i plleut, mett'ous yens 2023ÇŻĄĄ750ŁÍŁÌĄÊ„·ĄŒ„É„ëĄË
ČÌŒÂÌŁ€ż€Ă€Ś€ê€ÇżćĄč€·€€Ąą„Ô„ć„ą€ÊÌŁ€ï€€€Î„ô„Ą„ó„Ê„Á„ćĄŒ„ëĄȘ„í„ïĄŒ„ë€Ï„œĄŒ„ß„ćĄŒ„뀫€éÏĂÂê€Î„ô„Ą„ó„Ê„Á„ćĄŒ„ëĄȘșŁČó€Ï„€„ì„ź„ć„éĄŒ€â€ÎĄȘÁÄÉă€Ű€Î„Ș„ȚĄŒ„ž„ć€òčț€á€ż„·ĄŒ„É„ëĄő„·„ć„Ê„óĄő„Ț„ë„á„íĄő„·ĄŒ„É„ëĄȘ
3,508±ß(ÀÇ319±ß)
-

 „Ő„é„ó„œ„ïĄŠ„”„óĄŠ„íĄĄEune brave me, ch'pae ? 2023ÇŻĄĄ750ŁÍŁÌĄÊ„·„ć„Ê„óĄő„Ț„ë„á„íĄő„·ĄŒ„É„ëĄËÈùÈŻËą
„Ő„é„ó„œ„ïĄŠ„”„óĄŠ„íĄĄEune brave me, ch'pae ? 2023ÇŻĄĄ750ŁÍŁÌĄÊ„·„ć„Ê„óĄő„Ț„ë„á„íĄő„·ĄŒ„É„ëĄËÈùÈŻËą
ČÌŒÂÌŁ€ż€Ă€Ś€ê€ÇżćĄč€·€€Ąą„Ô„ć„ą€ÊÌŁ€ï€€€Î„ô„Ą„ó„Ê„Á„ćĄŒ„ëĄȘ„í„ïĄŒ„ë€Ï„œĄŒ„ß„ćĄŒ„뀫€éÏĂÂê€Î„ô„Ą„ó„Ê„Á„ćĄŒ„ëĄȘșŁČó€Ï„€„ì„ź„ć„éĄŒ€â€ÎĄȘÁÄÉă€Ű€Î„Ș„ȚĄŒ„ž„ć€òčț€á€ż„·ĄŒ„É„ëĄő„·„ć„Ê„óĄő„Ț„ë„á„íĄő„·ĄŒ„É„ëĄȘ
3,878±ß(ÀÇ353±ß)
-

 „É„áĄŒ„ÌĄŠ„é„żĄŒĄĄVdF„ëĄŒ„”„ó„Ì2023ÇŻĄĄ750ML
„É„áĄŒ„ÌĄŠ„é„żĄŒĄĄVdF„ëĄŒ„”„ó„Ì2023ÇŻĄĄ750ML
„íĄŒ„Ì€ÎÊÒĆČˀÇ€€é€ì€ëÁÇËрǿż€ĂÄŸ€°€ÊÌ”ĆșČĂ„Ê„Á„ć„é„ë„ï„€„óĄȘ„ł„č„È„Ń„Ő„©ĄŒ„Ț„ó„č€Î藀˶À€Ç€čĄȘ
3,324±ß(ÀÇ302±ß)
-

 „΄š„饊„â„é„ó„ż„óĄĄŁÖŁäŁÆ„·„§ĄŠ„·„ă„ë„륥„œĄŒ„ô„Ł„Ë„è„ó2022ÇŻĄĄ750ŁÍŁÌ
„΄š„饊„â„é„ó„ż„óĄĄŁÖŁäŁÆ„·„§ĄŠ„·„ă„ë„륥„œĄŒ„ô„Ł„Ë„è„ó2022ÇŻĄĄ750ŁÍŁÌ
„í„ïĄŒ„ë€Ï„È„„ĄŒ„ìĄŒ„Ì€ÎÈț€·€Ż„ß„Í„é„ê„Ł€Ê„ï„€„óĄȘ„΄š„éĄő„Ő„Ł„ê„Ă„Ś€Î„ï„€„óĄȘ€ä€Ï€ê„č„ż„€„ê„Ă„·„ć€ÇÄű€è€€¶ÛÄ„Ž¶žŠ€źÀĄ€Ț€”€ì€żŽ¶łĐłÚ€·€á€ë„ï„€„ó€Ç€čĄȘ
SOLD OUT
-

 „È„í„Ś„Ő„ë„ż„ë„Û„ŐĄĄ„í„Œ„Ț„êĄŒ2023ÇŻĄĄ750ML
„È„í„Ś„Ő„ë„ż„ë„Û„ŐĄĄ„í„Œ„Ț„êĄŒ2023ÇŻĄĄ750ML
„ô„Ł„Ê„€„ȘĄŒ„żÍÍ€è€ê„È„ì„ó„Æ„ŁĄŒ„ÎĄŠ„ą„ë„ÈĄŠ„ą„Ç„Ł„ž„§€ÎŸćŒÁ€Ç„脱ĄŒ„뎶€ą€ë„ï„€„óĆțĂć€Ç€čĄȘ
SOLD OUT
-

 „É„áĄŒ„ÌĄŠ„é„żĄŒĄĄVdF„ô„Ł„Ș„Ë„š2023ÇŻĄĄ750ML
„É„áĄŒ„ÌĄŠ„é„żĄŒĄĄVdF„ô„Ł„Ș„Ë„š2023ÇŻĄĄ750ML
„íĄŒ„Ì€ÎÊÒĆČˀÇ€€é€ì€ëÁÇËрǿż€ĂÄŸ€°€ÊÌ”ĆșČĂ„Ê„Á„ć„é„ë„ï„€„óĄȘ„ł„č„È„Ń„Ő„©ĄŒ„Ț„ó„č€Î藀˶À€Ç€čĄȘ
SOLD OUT